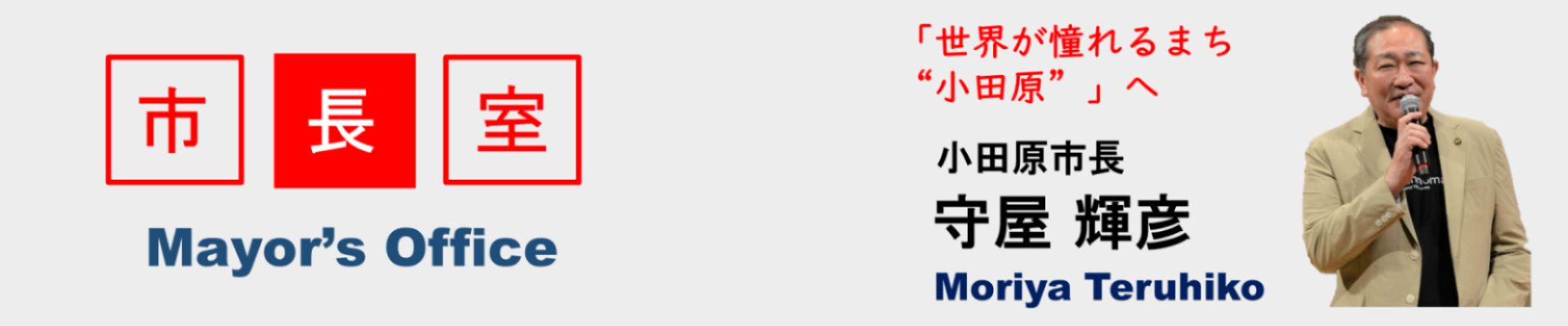14日は、城北タウンセンターいずみにて、「市民と市長の懇談会」として、子ども向けに活動をされている団体と子育て中の方にご参加いただき、「防災と子育て」をテーマに懇談を行いました。今回お集まりいただいたのは、防災についてのお話し会を実施されている「おだわら子ども防災」代表の箕輪さん、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各子育て支援センターの管理・運営をされている有限会社ぎんが邑RIV総合研究所取締役の川本さん、子育て支援センターを利用されている4名のお母さん方、計6名の方々です。
当日は、地域のブロック塀対策や災害時の避難の観点からの道路整備の必要性、備蓄食料の地産地消やアレルギー対策、授乳スペースの確保、保育園・幼稚園における防災意識の向上など、子育て中の方や子育ての現場に携わる方だからこそのご意見や、防災に対する意識などについてお聞きすることができました。小田原が好きで小田原愛にあふれている皆さん。お伺いしたご意見等を参考にしながら、安心して子育てができる地域社会の実現に向けて、しっかりと取組を進めてまいります。

15日昼は、小田原で獲れた「イシダイ」を使った学校給食「鯛めし」を試食しました。学校給食における「市内産活用倍増作戦」のキックオフとして企画された鯛めし給食。小田原の定置網で冬にまとまって獲れる高級魚イシダイに注目し、普段食べる機会の少ないイシダイの美味しさや小田原の魚の魅力を地元の小学生に知ってもらいたいとの思いから、漁業関係者や学校関係者の協力により「特別な給食」が実現しました。
3月10日から17日まで、市内20の小学校で提供され、私もこの日試食させていただきましたが、これが抜群に美味しい!力が湧いて心も身体も元気になりました。小田原市は農業・水産業が盛んですが、学校給食の市内産食材使用率は約14%にとどまっています。それを令和6年度までに25%以上にすることを目標に掲げた今回の倍増作戦。今後、小田原の豊富な食材を使った美味しい給食を提供していく予定ですので、今回の鯛めしの件も含め、学校給食の話題で家族の会話が弾む、そんな光景が増えてくれることを願っています。
その後は、市役所正面にて、陸上自衛隊駒門駐屯地第1高射特科大隊の隊区進出訓練における挨拶、激励を行いました。陸上自衛隊では災害対処の一環として、進出経路や現地確認、関係自治体との連携強化などを目的に、2市8町をエリアに実災害に即した訓練を実施しています。今年は関東大震災から100年の節目の年。改めて、大規模地震や大規模災害への備えの必要性を再認識するとともに、自衛隊との連携強化にも努めていきたいと思います。
16日は、マジカル・バラエティー・ライヴ事務局の皆さんが、5月6日三の丸ホール大ホールで行われるライブチケットの寄附のため、市長室にお越しくださいました。「驚き!笑い!小田原再発見LIVE!」が副題となっているこのイベントでは、小田原にちなんだマジックやコント、漫才、ボディパフォーマンスなどを披露されるとのこと。ゴールデンウィークの楽しみの一つとして、児童養護施設や子ども会の皆さんにお配りさせていただきます。ご厚意に感謝申し上げます。
16日夜は、小田原に誕生したコワーキングスペース「Work Place Market ARUYO ODAWARA(ワーク・プレイス・マーケット アルヨオダワラ)」で開催されている「ARUYO SNACK(アルヨスナック)」にお招きいただきました。ARUYO SNACKとは、様々な業界で活躍する起業家やビジネスパーソンをマスターとしてお呼びし、ARUYO ODAWARAのラウンジで参加者の皆さんと様々な話題について語り合うトークイベントです。
今回は私がマスターとなり、肩書も年齢も異なる6名の方々が参加。「今、世界と未来の話をしナイト。」と題し、ゆるく小田原のまちづくりのこと、自分自身のことをお互いに語り合いました。参加者同士の交流の中でアイデアやヒントが生まれたり、事業のきっかけになったり、新たな気づきを発見したりと、様々な効果が期待できると感じました。事前申込制でどなたでも参加できますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
17日は、非日常型体験学習実行委員会の委員の皆さんと懇談を行いました。 令和4年度の新規事業で、昨年7月30日から8月1日までの2泊3日で実施した、長野県飯田市にある「いろりの里 大平宿(おおだいらじゅく)」での体験学習では、市内小学生5・6年生17名が参加。電気と水道だけが残された廃村での自然体験を通して、学校や世代を超えた交流を深めました。
この体験学習で子どもたちをサポートしていただいたのが、今日お集まりいただいた非日常型体験学習実行委員会の皆さんです。下は16歳から上は71歳までの21名の方々で、それぞれ所属する団体で青少年活動を支えていただいています。皆さんの活動によって、小田原の将来の担い手である若者や子どもたちが大きく育っていくことを願っています。