広報おだわら 第1024号
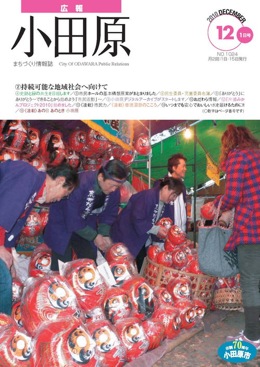
広報おだわら 第1024号
平成22年12月1日 発行
#01:持続可能な地域社会へ向けて
#02:史跡と緑の共生を目指します
#03:市民ホールの基本構想原案がまとまりました
#04:民生委員・児童委員名簿
#05:SHISEI〜至誠・市政〜
#06:「ありがとう」にありがとう〜できることから始めよう「市民活動」〜
#07:市制施行70周年事業小田原デジタルアーカイブがスタートします
#08:おだわら情報
#09:無尽蔵プロジェクトみかんの里からの贈り物「片浦みかんプロジェクト2010」始めました
#10:〈連載〉市民力
#11:〈連載〉尊徳道歌のこころ〈12〉(最終回)
#12:いつまでも安心でおいしい水を届けるために!!〜水道事業の現状と課題〜
#13:〈連載〉あの日 あのとき 小田原
#14:市制70周年記念特集号
PDF版
テキスト版
※以下のページは、目の不自由なかたでもご利用いただけるよう、市販の音声読み取りソフトに対応するため、文字データのみを記載しました。
====================
まちづくり情報誌 広報 小田原
12/1─12/15
平成22年12月1日発行 No.1024
====================
========目次========
#01:持続可能な地域社会へ向けて
#02:史跡と緑の共生を目指します
#03:市民ホールの基本構想原案がまとまりました
#04:民生委員・児童委員名簿
#05:SHISEI〜至誠・市政〜
#06:「ありがとう」にありがとう〜できることから始めよう「市民活動」〜
#07:市制施行70周年事業小田原デジタルアーカイブがスタートします
#08:おだわら情報
#09:無尽蔵プロジェクトみかんの里からの贈り物「片浦みかんプロジェクト2010」始めました
#10:〈連載〉市民力
#11:〈連載〉尊徳道歌のこころ〈12〉(最終回)
#12:いつまでも安心でおいしい水を届けるために!!〜水道事業の現状と課題〜
#13:〈連載〉あの日 あのとき 小田原
#14:市制70周年記念特集号
====================
====================
#01:持続可能な地域社会へ向けて
====================
問 地域政策課 電話0465-33-1389
地域コミュニティ検討委員会から報告書が提出されました
平成20年11月に設置された「地域コミュニティ検討委員会」では、市民が主役となり、知恵と力を発揮し、生きる喜びを実感しながら暮らし続けることができる「持続可能な市民自治のまち」を可能にする、小田原ならではの地域コミュニティの在り方を検討してきました。
ここでは10月21日に検討委員会から提出された報告書の主な内容をお伝えします。
報告書では、まず、本市における地域コミュニティの現状を分析し、望まれる地域コミュニティの将来像が示されています。
そして、その将来像を実現するための新たな地域コミュニティに必要な3つの機能、それらを可能とする新たな仕組みとなる「地域運営協議会」や、市の支援体制について述べられています。
--------------------
地域コミュニティの現状と将来像
--------------------
●地域を取り巻く環境の変化によって、連帯意識の希薄化や協力体制の低下から、解決の難しいさまざまな問題が現れ始めている。
●平成21年度の地域別計画策定のように課題の把握や目標の共有、解決に向けて共に行動することを可能とする新たな連携が必要である。
--------------------
地域コミュニティに必要な3つの機能
--------------------
モデル事業の実施などを通じて確認された新たな地域コミュニティに必要な機能は次の3つである。
●各種団体の新たな連携
●コーディネーター役として求められる人材
●参加したくなる交流の場の創出
--------------------
新たな地域コミュニティの仕組み
--------------------
新たな地域コミュニティの仕組みとして、課題にきめ細かく対応し、地域全体を包括する組織である「地域運営協議会」が必要である。
【地域運営協議会】(以下協議会)
協議会の設立については、行政が仕組みを設定するのではなく、地域が一丸となって課題解決へ取り組むという意識を共有したうえで、そのための連携組織が必要と認識し、行政と一緒に議論しながら連携組織をつくった結果、協議会ができるようなプロセスが好ましい。
◆協議会の区域
地区自治会連合会の区域が望ましい。
◆協議会の事務局
運営には、事務局機能が必要であり、地域主体の運営を行うために、地域住民が事務局を担うことが望ましい。
◆既存団体との関係
協議会設立後も、既存団体の重要性は変わることなく、協議会の各部会の中で他団体との協働を担う一方、独自の活動を継続することがよい。
◆市との関係
地域を代表する組織として市が認定すること、また、市と協働を進めるパートナーとして、協定を締結することが望ましい。
◆合意形成の仕組み
意思決定は、透明性、公平性などを確保しながら多くの住民の意思に沿った合意形成を可能とする仕組みが望まれる。
◆担い手の確保
日常の地域活動の中で声かけなどを大事にし、PTAや団塊の世代などにアプローチしていくことが重要である。
◆財源の確保
地域においては自主財源の確立も望まれるが、課題の解決に向けた新たな連携の枠組みを設け、行政とともに協議、実践するという場合には、行政もその費用の一部を負担していくことが必要である。
--------------------
市の支援体制
--------------------
●地域担当職員は、協議会の設立に向けた支援を行うほか、行政と地域とのパイプ役となって協議会運営をサポートしていく。
●全ての区域における協議会の活動を支える活動拠点の配置を基本方針とすべきであるが、市の財政状況や地域の財源の規模から、直ちに全ての地区に整備することは困難であり、現在利用されている公共施設や民間施設の活用を継続していくべきである。
市では、この報告書の提出を受け、協議会の設立などに向けた制度や庁内体制の検討・整備を行い、協議会設立に向けた準備が整った地区の相談への対応や支援をしていく予定です。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
小田原の地域の可能性を感じています
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
地域コミュニティ検討委員会委員長
法政大学法学部教授
名和田 是彦さん
今、小田原市だけではなく、日本全国の自治体で、地域コミュニティの再建、新しいコミュニティの確立が試行錯誤されています。
地域社会に適したコミュニティの在り方を研究している私は、小田原市の大きな可能性を感じています。地域で活動している人やそれぞれの団体が、横の連携を強めて相乗効果を発揮することがこれから必要であることを、多くの市民が気づいているからです。
この報告書では、その連携の具体的な姿を提言しています。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
地域活動の幅広い連携を目指して
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
地域コミュニティ検討委員会副委員長
市自治会総連合会長
石川 信雄さん
自治会代表として、市長から委員を委託されました。自治会が健全に歩んでいるのは、諸先輩方の努力の賜物であり、地域への強い愛着がある各種団体や委員の皆様の協力のおかげです。
この委員会には各種団体の代表のかたが参加され、2年間にわたってさまざまな面から議論することができました。地域と市の役割を考え、今後の地域活動における団体間の幅広い連携や、地域住民の安全安心で住みよいまちづくりを目指すうえで、有意義であったと思います。
====================
#02:史跡と緑の共生を目指します
====================
問 文化財課 電話0465-33-1718
『史跡小田原城跡本丸・二の丸植栽管理計画』を適切に推進していくために運用指針を策定しました。
広報おだわら8月1日号などで紹介している『史跡小田原城跡本丸・二の丸植栽管理計画』を適切に推進していくために、植栽専門部会の設置などを定めた運用指針を策定しました。
この運用指針は、御用米曲輪などの史跡の整備事業に併せて行う植栽管理や、史跡整備を待たずに実施する「短期実施計画」に位置づけられた植栽管理を具体的に進めていくための方針を定めたもので、史跡と緑の共生を図りながら植栽管理作業を進めることを理念としています。
●植栽専門部会の設置
史跡整備や、「短期実施計画」の植栽管理作業を具体的に進める組織として、植栽専門部会を設置します。この専門部会は、小田原城跡の整備を円滑に行うために設置されている史跡小田原城跡調査・整備委員会のもとに置きます。
[ 委員の構成 ]
植栽専門部会は史跡小田原城跡調査・整備委員会の城郭・都市工学・造園を専門とする委員のほか、植物、環境、造園技術等の分野の専門家、市民で構成します。
[ 設置時期 ]
平成22年度中に設置します。
●植栽管理計画の今後の進め方
[ 植栽専門部会での検討 ]
史跡整備における植栽のあり方について、今ある樹木を1本1本どのようにしていくのか、また新たな植栽をどのようにしていくのかなど、計画の策定段階から植栽専門部会において協議し、史跡整備計画案に反映していきます。
また、「短期実施計画」に位置付けた樹木については、植栽専門部会においてどの場所から行うか協議のうえ、1本1本現地で具体的に検証し、実施計画案(*)をまとめます。
*ここでいう実施計画案は、伐採が必要と判断したり、枝下しや整枝が必要な樹木についてどのような姿がふさわしいかなど、実際に作業を行う造園業者に具体的に指示していくためのものです。
[ 市民意見の集約 ]
植栽専門部会が取りまとめた史跡整備計画案や実施計画案については、市民説明会や現地見学会を開催し、これらに対する市民の意見や提案を集約して、可能な限り反映させます。
[ 計画案の協議・決定 ]
こうした過程を経て練り上げた計画案を、史跡小田原城跡調査・整備委員会等と協議し、その成果をもって市教育委員会が成案(決定)とします。
[ 計画の許可等 ]
計画のうち、文化財保護法に基づく現状変更許可申請が必要な場合は、神奈川県教育委員会を通じて文化庁の許可を得ます。
史跡小田原城跡は、豊かな歴史を持ち、海外からも多くの観光客が訪れるかけがえのない郷土の文化遺産です。市では、こうした場所として市民や観光客の皆さんに、これまで以上、安全に快適に利用していただけるよう、史跡と緑の共生に努めてまいります。
====================
#03:市民ホールの基本構想原案がまとまりました
====================
問 文化交流課 電話0465-33-1706
昨年12月に設置された「市民ホール建設準備会」では、市民ホール整備の基本理念や基本方針など、ホール整備の核となる事柄について議論を重ねてきました。
この度、これまでの検討結果がまとまり、市に報告されました。
市では、開館から約半世紀が過ぎ、老朽化した小田原市民会館に代わり、これからの時代にふさわしい市民の新たな芸術文化創造の拠点となる施設として、市民ホールの整備を進めています。
●準備会による検討
市では、昨年12月、学識経験者やホールの専門家、市の文化団体代表者などをメンバーとする「市民ホール建設準備会」を設置しました。
準備会では、まず「市民ホール基本構想」の原案策定に取り組みました。これまで12回の会議を開催し、このうち1回は市民と準備会委員との「意見交換会」を行いました。また、議論を深めるため、都内や県内にある先進的な公立文化施設の視察も行いました。
●基本構想原案のポイント
この度、準備会では、これまでの検討結果をとりまとめ、「市民ホール基本構想」の原案として市に報告しました。
準備会が取りまとめた「市民ホール基本構想」の原案では、市民ホールには、芸術文化をとおして市民の創造性を喚起し、小田原の歴史・文化的な資産を拓く役割があることを明記しています。同時に、コミュニティを活性化させ、地域経済の発展に寄与することを求めています。また、市民ホール整備は、小田原を文化創造都市として発展させていくために必要な「未来への投資」であるとしています。
このほか、大小ホールや展示施設などの内容、管理運営手法、市民参加の重要性や、景観への配慮、今後の整備に当たっての提言などが盛り込まれています。
●今後の市の取り組み
今後、準備会の原案をもとに、「市民ホール基本構想」を策定します。さらに、これを実現するため、より具体的なことを定めた基本計画の策定や、拡張用地の取得を進めます。
市では、市民ホール整備を通じてさまざまな芸術文化事業や運営を市民参加により展開することで、小田原が本来持っていた魅力を磨き、まちに活力をあふれさせる、そうした将来像を、市民の皆さんと一緒に描いていきたいと考えています。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
【ホームページ】
トップページ中央の「分野別から探す」の「生涯学習/文化」内の「市民ホール」をクリック。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
●説明会を開催します
市では、準備会が取りまとめた「市民ホール基本構想」の原案を、市民の皆さんにご説明します。お気軽にお越しください。
【市民会館会場】1月13日木曜日午後6時〜8時
【マロニエ会場】1月14日金曜日午後6時〜8時
※事前申し込みは不要です。
●意見を募集します
「市民ホール基本構想」の原案に対する市民の皆さんの意見を募集します。原案は市役所文化交流課、支所・連絡所、市ホームページなどでご覧になれます。
【募集期間】12月13日月曜日〜平成23年1月21日金曜日
【意見提出方法】募集用紙に意見を記入し、郵送またはファクスなどにより提出してください。
※ご意見に対して個別には回答しません。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
====================
#04:民生委員・児童委員名簿
====================
問 福祉政策課 電話0465-33-1863
12月1日からの民生委員・児童委員(区域担当273名、主任児童委員50名)が決まりました。
民生委員・児童委員は地域内のいろいろな福祉問題の最も身近な相談相手です。
プライバシーは尊重され、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
地区名 担当 氏名 電話の順
緑 1区-1 佐野都 0465-35-4680
緑 1区-2 中井敬子 0465-24-2300
緑 2区-1 山崎叔子 0465-22-2368
緑 2区-2 古川正夫 0465-22-7567
緑 3区 山口正隆 0465-23-1216
緑 浦町 関野フミエ 0465-23-1735
緑 4区 染野ひで子 0465-22-3447
緑 5区 真壁洋善 0465-22-4804
緑 竹花 高野博幸 0465-22-0165
緑 銀座 松本明 0465-22-2609
緑 主任児童委員 池田法枝 0465-22-3907
緑 主任児童委員 小林泰一郎 0465-22-1960
新玉 台宿・大工町 黒柳喜昌 0465-22-3566
新玉 9区 須山晴夫 0465-24-1743
新玉 10区 田口正道 0465-22-0755
新玉 11区 石田翠 0465-22-7898
新玉 12区 中島秀子 0465-22-0647
新玉 13区 進藤邦江 0465-22-3319
新玉 14区 村山京子 0465-22-5727
新玉 主任児童委員 絞結清美 0465-24-6872
新玉 主任児童委員 山崎由起子 0465-23-1230
万年 15区 菊地洋一 0465-22-2730
万年 16区 石黒省二 0465-22-7701
万年 17区 中島公子 0465-22-9084
万年 18区 石田玲子 0465-23-2004
万年 19区 加藤マツエ 0465-22-5936
万年 20区-1 泰田幸枝 0465-22-9409
万年 20区-2 宮本純 0465-22-0097
万年 主任児童委員 山田昭子 0465-22-1137
万年 主任児童委員 和田真理 0465-24-5420
幸 21区-1 田近公榮 0465-22-0153
幸 21区-2 12月1日現在未定
幸 22区 藤間敬子 0465-22-9744
幸 23区 尾上弘美 0465-23-0375
幸 24区 鈴木美知子 0465-22-3229
幸 25区 加藤芳 0465-22-3851
幸 26区 望月政江 0465-21-1558
幸 27区-1 川原裕子 0465-23-0957
幸 27区-2 朝見美子 0465-22-3624
幸 主任児童委員 石川啓子 0465-22-6052
幸 主任児童委員 相田春子 0465-22-7817
十字 28区 五十嵐博 0465-23-2127
十字 29区 小野美代子 0465-22-5645
十字 30区 目良幸子 0465-23-2886
十字 31区 本多孝 0465-22-5270
十字 32区-1 中津川真基子 0465-24-5665
十字 32区-2 込山ひろ子 0465-22-0197
十字 主任児童委員 小西道子 0465-24-3482
十字 主任児童委員 京増ふく江 0465-24-0890
足柄 33区・セントラルハイツ 瀬戸昌子 0465-22-6672
足柄 34区 田村美津子 0465-24-3047
足柄 35区 山岸勝 0465-23-3046
足柄 36区-1 山田敏夫 0465-23-6458
足柄 36区-2 上田純子 0465-32-8700
足柄 36区-3 石川美和子 0465-34-4762
足柄 37区-1 三宅恵鐘 0465-34-9712
足柄 37区-2 野島千津子 0465-35-3545
足柄 主任児童委員 出野正一 0465-34-0017
足柄 主任児童委員 青柿節子 0465-24-6806
芦子 寺町-1 山口亘子 0465-34-4431
芦子 寺町-2 小林節恵 0465-35-6068
芦子 荻窪-1 浜崎政廣 0465-35-7335
芦子 荻窪-2 田中里美 0465-34-0334
芦子 荻窪-3 本多美恵子 0465-34-4251
芦子 荻窪-4 久保恒明 0465-34-9198
芦子 下谷津 高田良子 0465-35-0222
芦子 中谷津 南千恵子 0465-34-3639
芦子 上谷津 藤田容子 0465-34-3660
芦子 入谷津 岡田健 0465-34-7125
芦子 池上-1 市川初江 0465-34-2648
芦子 池上-2 堀川清子 0465-30-2727
芦子 主任児童委員 岡部和江 0465-34-2704
芦子 主任児童委員 田中眞理子 0465-34-5656
二川 井細田1区-1 別生憲一 0465-34-7176
二川 井細田1区-2 小澤良弘 0465-35-1737
二川 43区-1 山田泰彦 0465-34-5516
二川 43区-2 永田久美子 0465-35-8308
二川 44区-1 長井和子 0465-34-1540
二川 44区-2 佐久間紀子 0465-34-6232
二川 44区-3 野頼じゅん子 0465-34-0176
二川 グリーンタウン 馬場潤子 0465-35-6170
二川 主任児童委員 横山孝之 0465-35-5108
二川 主任児童委員 磯崎英里 0465-32-4634
東富水 蓮正寺第1南 津田仁 0465-36-3419
東富水 蓮正寺第1北 齊藤義博 0465-36-3793
東富水 蓮正寺第2 長尾戴治 0465-37-0326
東富水 蓮正寺第3 神野功二 0465-37-1475
東富水 蓮正寺第4 磯崎伸子 0465-36-3213
東富水 蓮正寺第5 木村晃一 0465-36-2829
東富水 蛍田駅前・蓮正寺住宅 塚田正子 0465-37-7408
東富水 蛍田中央 澤地松次郎 0465-36-4857
東富水 霞ノ瀬・狩川 原島幸子 0465-37-3958
東富水 蛍生会-1 中島喜芳 0465-57-7195
東富水 葭田・蛍生会-2 星野優子 0465-36-4971
東富水 飯田岡東 榊昭子 0465-36-4645
東富水 中曽根-1 飯田ヨシ子 0465-37-4587
東富水 中曽根-2 佐藤時代 0465-36-6811
東富水 中曽根-3 諏訪部絹恵 0465-36-5811
東富水 堀之内東 酒口松男 0465-36-3555
東富水 堀之内中 岩崎臣男 0465-36-7634
東富水 堀之内西 阿部千津子 0465-37-3855
東富水 主任児童委員 石坂照子 0465-36-1760
東富水 主任児童委員 石井恵子 0465-36-4644
富水 飯田岡本村 橋本尚信 0465-36-2755
富水 飯田岡若宮 高橋しのぶ 0465-36-1082
富水 飯田岡飯中 内田敬子 0465-36-1298
富水 飯田岡楠 大澤孝子 0465-35-2901
富水 柳新田 渡邉みどり 0465-37-1959
富水 小台 市川昭維子 0465-36-0032
富水 池田 中野桂子 0465-36-4075
富水 新屋-1 鍵和田健治 0465-36-2208
富水 新屋-2 木村幸枝 0465-36-0534
富水 府川 矢ヶ村直廣 0465-34-8983
富水 久所 井上奈美子 0465-32-7769
富水 仲沢 山口ひさ 0465-34-4225
富水 北ノ窪-1 木村栄子 0465-34-5765
富水 北ノ窪-2 押田房枝 0465-34-7744
富水 上清水新田 馬場照子 0465-36-4876
富水 下清水新田 岩田紀孝 0465-32-7080
富水 穴部-1 松谷いづみ 0465-34-8144
富水 穴部-2 鶴井美恵子 0465-34-0129
富水 穴部新田 小林財子 0465-35-1486
富水 主任児童委員 柳井由美子 0465-38-0532
富水 主任児童委員 佐々木恵生 0465-37-0473
久野 宮本-1 眞嶋敏子 0465-34-1820
久野 宮本-2 服部俊男 0465-35-2003
久野 宮本-3 久保寺征一 0465-34-7796
久野 坂下-1 多田幸雄 0465-34-4088
久野 坂下-2 松浦正 0465-34-9186
久野 京福台・北久保 岡村悦子 0465-34-1649
久野 下宿-1 江木和子 0465-34-4772
久野 下宿-2 辻美智子 0465-34-9915
久野 中宿 遠藤譲 0465-34-1045
久野 星山 掬川光美 0465-34-4411
久野 中久野 星野操 0465-34-0889
久野 留場・坊所 山崎量一 0465-34-5299
久野 三国・欠ノ上 小石川美津代 0465-35-1055
久野 船原・諏訪原・和留沢 戸倉次朗 0465-34-8531
久野 サニータウン 12月1日現在未定
久野 主任児童委員 山田悦子 0465-35-7313
久野 主任児童委員 田中由香里 0465-34-3570
大窪 58区 田島昭子 0465-23-7607
大窪 59区-1 12月1日現在未定
大窪 59区-2 矢吹昭子 0465-22-8453
大窪 60区 住吉律子 0465-22-8419
大窪 61区-1 伊藤由紀子 0465-23-4032
大窪 61区-2 巽美智子 0465-22-0148
大窪 62区-1 秋山和恵 0465-23-2085
大窪 62区-2 服部ふく江 0465-22-1887
大窪 63区 川向良江 0465-22-4210
大窪 64区 秋山悦子 0465-22-1718
大窪 主任児童委員 山田信子 0465-23-7400
大窪 主任児童委員 川向由起子 0465-23-7632
早川 木地挽-1・2 加藤信子 0465-23-0664
早川 木地挽-3 小野利枝 0465-22-1337
早川 木地挽-4 下田勝也 0465-22-0176
早川 早稲田 伊藤初恵 0465-22-2893
早川 向口 青木かつ子 0465-22-4385
早川 西組 青木美恵子 0465-22-0084
早川 中組 青木祐伸 0465-23-2522
早川 東組 露木弘子 0465-22-1271
早川 主任児童委員 相原久花 0465-23-4564
早川 主任児童委員 佐藤直美 0465-22-7824
山王網一色 山王松原 花田昭恵 0465-22-2005
山王網一色 山王西 吉田敏子 0465-34-4616
山王網一色 山王東 島田久恵 0465-35-6772
山王網一色 70区-1 齋藤茂子 0465-35-6743
山王網一色 70区-2 岩田隆一 0465-35-5451
山王網一色 70区-3 太田武子 0465-34-1633
山王網一色 網一色-1 金親善学 0465-34-9542
山王網一色 網一色-2 野月繁乃 0465-35-7605
山王網一色 主任児童委員 多田千佳代 0465-35-5911
山王網一色 主任児童委員 露木光訓 0465-34-2046
下府中 下堀(東) 吉田好男 0465-42-3457
下府中 下堀(西) 小林君子 0465-42-5117
下府中 中里1区-1A 磯崎至 0465-42-2964
下府中 中里1区-1B 大島安治 0465-42-0798
下府中 中里1区-2 原幸造 0465-42-1445
下府中 中里2区-1 渡邉洋子 0465-48-3595
下府中 中里2区-2 松村いづみ 0465-48-2109
下府中 矢作(下) 高橋裕子 0465-48-3185
下府中 矢作(上) 田中美恵子 0465-47-2295
下府中 南鴨宮1区 香坂功喜 0465-48-5507
下府中 南鴨宮2区-1 小嶋祥溥 0465-47-6977
下府中 南鴨宮2区-2 藤本恵美子 0465-48-2129
下府中 南鴨宮3区 須田玲子 0465-47-9085
下府中 南鴨宮4区 山岸都子 0465-48-3931
下府中 南鴨宮5区 平川幸子 0465-47-2541
下府中 鴨宮2区-1 天野久美子 0465-47-8153
下府中 鴨宮2区-2 尾崎徹 0465-48-2579
下府中 鴨宮3区 鈴木新一 0465-49-2838
下府中 鴨宮4区-1 秋澤益美 0465-48-8859
下府中 鴨宮4区-2 中島久美 0465-43-7253
下府中 鴨宮5区-1 津田典信 0465-48-6271
下府中 鴨宮5区-2 古藤みどり 0465-47-3081
下府中 大道 三好幸枝 0465-47-5293
下府中 主任児童委員 柏木英幸 0465-49-2306
下府中 主任児童委員 杉山久恵 0465-47-9279
桜井 寺下・浅原 南雲賢子 0465-37-3986
桜井 高河原-1 砂子幸子 0465-37-3605
桜井 高河原-2 高橋昇子 0465-36-3976
桜井 河原庭 秋山恵美子 0465-36-9049
桜井 西之庭・新屋敷 内田美枝子 0465-36-8364
桜井 柳町・清流荘 邊見直美 0465-37-6512
桜井 東栢山学校前(東) 窪田きみ 0465-36-3726
桜井 東栢山学校前(西) 長崎民夫 0465-36-3510
桜井 東栢山城北-1 中村悦子 0465-36-9468
桜井 東栢山城北-2 小泉美智代 0465-37-9341
桜井 東栢山道下 小澤治枝 0465-37-0589
桜井 東栢山中の町 若林とも子 0465-36-0301
桜井 東栢山道上-1 小松敏男 0465-37-2261
桜井 東栢山道上-2 安藤昭男 0465-36-0231
桜井 西栢山(東) 木村哲郎 0465-36-1069
桜井 西栢山(西) 安藤邦子 0465-36-8646
桜井 弥生-1 新井マサ子 0465-37-1570
桜井 弥生-2 和木公子 0465-37-8445
桜井 主任児童委員 渡邉裕美 0465-37-5310
桜井 主任児童委員 高橋ひとみ 0465-36-0910
豊川 飯泉1区西 門松一枝 0465-47-4540
豊川 飯泉1区北 山室秀子 0465-48-7688
豊川 飯泉1区南 門松利親 0465-48-2697
豊川 飯泉2区 八森綾子 0465-48-4726
豊川 飯泉3区 片倉静江 0465-47-9000
豊川 東成田(下)-1 湯本悦子 0465-36-7023
豊川 東成田(下)-2 米山友規枝 0465-37-1552
豊川 東成田(上)・成和 栢沼千代美 0465-36-4363
豊川 西成田 松下範子 0465-36-6542
豊川 桑原-1 澤地すみ子 0465-36-4463
豊川 桑原-2・富士見 加藤和子 0465-36-6004
豊川 主任児童委員 水野秀子 0465-47-3872
豊川 主任児童委員 佐藤公生 0465-36-7100
上府中 高田別堀西 足立美和子 0465-42-2878
上府中 高田別堀南 長谷川トキ子 0465-42-4040
上府中 高田別堀東 高野昭芳 0465-42-4080
上府中 上千代-1 杉山輝雄 0465-42-2750
上府中 上千代-2 田邉淳子 0465-42-1575
上府中 上原 富田麻里 0465-42-1557
上府中 下千代 小塩千恵 0465-42-4366
上府中 永塚-1 木村絹代 0465-42-6765
上府中 永塚-2 田辺紀子 0465-42-1277
上府中 東大友 吉本順 0465-42-1594
上府中 西大友 松嶋克夫 0465-36-2485
上府中 延清 伊東たか子 0465-36-7960
上府中 主任児童委員 石井律子 0465-42-2205
上府中 主任児童委員 長谷川住子 0465-37-7566
下曽我 曽我原 穂坂富幸 0465-42-0108
下曽我 曽我谷津 長谷川悦子 0465-42-1097
下曽我 曽我岸・曽我山岸 浅海弘子 0465-42-0928
下曽我 曽我別所 穂坂幸子 0465-42-2711
下曽我 曽我神戸 竹下啓子 0465-42-0711
下曽我 主任児童委員 佐宗昌子 0465-42-0645
下曽我 主任児童委員 小泉由利子 0465-42-1184
国府津 国府津1区・2区 亀田裕三 0465-47-1303
国府津 国府津3区・4区 星野明美 0465-48-0235
国府津 国府津5区・6区 倉橋準一 0465-48-0249
国府津 国府津7区 神尾彰野 0465-47-4496
国府津 国府津8区 和田典子 0465-47-2683
国府津 国府津9区 大川紀江 0465-48-8883
国府津 国府津10区-1 尾上巽 0465-47-7518
国府津 国府津10区-2 岸治恵 0465-47-6655
国府津 国府津11区-1 細谷洋子 0465-47-7395
国府津 国府津11区-2 山田和子 0465-48-0434
国府津 国府津11区-3 長谷川弥生 0465-48-2855
国府津 国府津12区 下川雅江 0465-42-0909
国府津 国府津13区・14区 野地富江 0465-42-0943
国府津 国府津15区-1 折金典男 0465-48-2962
国府津 国府津15区-2・19区 和田幸夫 0465-48-0575
国府津 国府津16区 田代篤子 0465-48-3381
国府津 国府津18区 岩沢好子 0465-48-9387
国府津 主任児童委員 矢島ケイ子 0465-47-6176
国府津 主任児童委員 石井孝代 0465-48-8198
酒匂 酒匂1区・17区 布施實 0465-48-7884
酒匂 酒匂2区・4区 坂田逸司 0465-47-8539
酒匂 酒匂3区・13区 磯崎一子 0465-47-8433
酒匂 酒匂5区・15区 金森優子 0465-47-4867
酒匂 酒匂6区 金沢幸子 0465-48-7654
酒匂 酒匂7区・14区 鈴木一郎 0465-47-5260
酒匂 酒匂8区-1 堀内勇 0465-47-4217
酒匂 酒匂8区-2 中津滋 0465-49-6268
酒匂 酒匂9区・10区 日下部透 0465-48-5467
酒匂 酒匂11区-1 二見昭 0465-48-2655
酒匂 酒匂11区-2・16区 和田智恵子 0465-48-4769
酒匂 酒匂12区-1 鎌田信子 0465-48-6669
酒匂 酒匂12区-2 木目田マリ子 0465-48-0022
酒匂 小八幡1区-1・2区-2 大木雅子 0465-47-3629
酒匂 小八幡1区-2・2区-1 寺島美枝子 0465-48-0098
酒匂 小八幡3区・4区 鈴木修一 0465-47-5614
酒匂 小八幡5区・6区 高澤衛 0465-48-4777
酒匂 小八幡8区 片瀬清 0465-48-7135
酒匂 小八幡9区・10区 上原雪代 0465-48-4134
酒匂 主任児童委員 島津三喜子 0465-48-6930
酒匂 主任児童委員 高橋美智子 0465-47-5013
片浦 石橋 山岸輝雄 0465-23-1399
片浦 米神 松本公子 0465-22-7673
片浦 根府川 山本由美子 0465-29-0064
片浦 江之浦 高橋卓也 0465-29-0652
片浦 主任児童委員 海野みち子 0465-29-0503
片浦 主任児童委員 櫻井千史 0465-29-0729
曽我 上曽我・曽我大沢 星野千恵子 0465-42-2053
曽我 中河原・明月・山岸 代田要 0465-42-1069
曽我 下大井 長田康子 0465-37-8766
曽我 鬼柳 杉崎和子 0465-36-2583
曽我 春木 日野岡美和子 0465-37-1707
曽我 籠場 湯川哲夫 0465-57-0183
曽我 花里 池貝みさ子 0465-36-7142
曽我 主任児童委員 前場典子 0465-42-5002
曽我 主任児童委員 野坂道代 0465-36-5700
橘南 西1区・2区・JRアパート 椎野尚 0465-43-1802
橘南 中宿 本田育郎 0465-43-0097
橘南 向原 遠藤芙美枝 0465-43-1710
橘南 町屋 石塚八重子 0465-43-1648
橘南 押切・羽根尾 小澤安子 0465-43-2126
橘南 主任児童委員 富瀬一枝 0465-43-2697
橘南 主任児童委員 増井幸美 0465-43-3439
橘北 中村原1区・住宅 内藤克子 0465-43-3141
橘北 中村原2区 長谷川礼子 0465-43-1557
橘北 中村原3区・6区・7区 飯田一枝 0465-43-0130
橘北 小船1区 志澤俊之 0465-43-0116
橘北 小船2区・山西 佐藤一夫 0465-43-0696
橘北 小竹(下・坂呂・打越・脇)・明沢 小澤照良 0465-43-0723
橘北 上町・沼代 真壁一夫 0465-43-0381
橘北 橘団地一般住宅 加藤嘉彦 0465-43-0868
橘北 橘団地共同・若葉台 酒井正 0465-43-4461
橘北 さつきが丘・湘南橘台 相田裕二 0465-43-3325
橘北 主任児童委員 小宮博子 0465-43-0526
橘北 主任児童委員 北薮ルミ 0465-43-4870
====================
#05:SHISEI〜至誠・市政〜
====================
「小田原を盛り上げる民の力」
文 加藤憲一
私は市長就任以降、「希望と活力あふれる小田原」を目指し、地域経済振興や市民活力向上につながるさまざまな取り組みを立ち上げ、またそれに呼応する民間の動きを促してきました。ここに来てそれらの仕込みが徐々に形になりつつあり、心強く思っています。
まずひとつは、小田原の中からの動き。小田原がもつ地域資源に着目し、10のテーマで昨年12月にスタートした「無尽蔵プロジェクト」は、具体的な動きが活発化しています。「ウォーキングタウン小田原」では、清閑亭を拠点としたウォーキングイベントや多彩な文化芸術活動などが繰り広げられ、活況を呈しています。「食の小田原」では、子どもから大人まで一緒に安全な食を生み出す教育ファームづくりが進み、マルシェ(市場)が開催されるようになりました。「ものづくり・デザイン・アート」では、地場の伝統工芸の担い手と、新しく小田原で活動を始めた工芸・芸術の担い手の交流が始まりました。「小田原ならではの住まいづくり」では、小田原産木材が強度的に問題ないことが立証され、家づくりやまちづくりにおける木の活用へと検討が進みつつあります。10のテーマ以外にも、新たなテーマが民間団体の皆さんから持ち込まれ、その裾野はさらに広がっています。
もうひとつは、小田原の外からの動き。先行き不透明な時代の中、豊かな生活文化を育てたり、持続可能な社会システムづくりへのチャレンジが、官民を問わずさまざまな地域や分野で進んでいたりしますが、それらの情報や担い手の交流、さらには新しいモデル作りなどの全国区の動きが、小田原を舞台に行われることが増えているのです。例えば、「木の建築フォーラム」(10/16〜17)では、国内屈指の林業事業者や、木造建築の権威、まちづくり分野の専門家などが集い、「小田原を優れた木造建築のメッカにし、その分野を目指す若者たちの学びの場にしてはどうか。力になりたい」とのエールを頂きました。また、これからの地域づくりや人づくりを語り合う「第3回ローカルサミット」(10/22〜24)では、主催者から「小田原には羨ましいくらい全ての素材がそろっている。新しい時代に向けての小田原モデルをつくろう。私たちも応援する」との激励。このような提案が、ほかにも持ち込まれています。小田原における「持続可能な市民自治のまち」への官民のさまざまな活動やビジョンに共鳴もしくは呼応した人や情報が、集まりつつあるのです。
小田原の内から外から、民の力が小田原を元気にしようと動き始めています。この流れをしっかりと捉え、小田原を大きく育てるうねりにしていきましょう。
====================
#06:「ありがとう」にありがとう〜できることから始めよう「市民活動」〜
====================
問 地域政策課 電話0465-33-1458
「地域や社会のために、自分にできることを、まずやってみよう!!」という気持ちを原動力に行う市民活動。今まで、「奉仕」というイメージが強かったボランティア活動も、市民活動の一つであり、地域貢献や自己実現の一つの手段として「自分のやりたいことを形にする」「自分にできることが誰かの役に立っている」という生きがいや、やりがいにつながっています。
何げなく行ったことに「ありがとう」と言われて、うれしかったことはありませんか?どんな小さなことでも、「自分のため」ではなく「必要としている人のため」に行うことが市民活動です。
まずは、興味のある分野で、できる範囲で、第一歩を踏み出してみませんか。
チャレンジ、市民活動!
〜皆さんを応援します〜
市では、たくさんの「ありがとう」があふれる、豊かなまちづくりを目指しています。市民活動を応援するいろいろな制度をぜひご活用ください。
--------------------
感謝を伝える
--------------------
まごころカード
市民活動をたたえあう社会を目指し、市長が市民を代表して感謝の意を伝えるために発行するカードです。自薦・他薦は問いません。
--------------------
支援相談
--------------------
おだわら市民活動サポートセンター
ミーティングルームや作業スペースの利用、印刷機などの提供といった市民活動団体への支援だけでなく、市民活動についての相談を受け、活動団体やイベントなどの具体的な紹介を行っています。
場所 市民会館4階 電話0465-22-8001
開所時間
午前9時〜午後9時30分
休館日
月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)・年末年始
--------------------
補助金制度
--------------------
市民活動応援補助金
○「始めてみよう」は
スタートアップコース
(上限10万円)
○「より良くしよう」は
ステップアップコース
(上限30万円・対象事業費の1/2以内)
「活動資金が足りない」という団体を後押しするための補助制度です。
これから始めようとする事業が対象のスタートアップコースと、すでに実施していることをより発展・拡充する事業が対象のステップアップコースの2つのコースがあります。申請書類や公開プレゼンテーションによって事業内容を審査し、交付事業を決定します。
現在、平成23年度の交付事業を、平成23年1月21日金曜日まで募集しています。
詳しくは、公共施設に設置してある応募の手引きまたは市ホームページをご覧ください。
--------------------
補償制度
--------------------
ボランティア活動補償制度
皆さんが市民活動を行っているとき(活動場所への行き帰りを含む)に起こった事故に対する補償制度です。事前登録は不要です。
※対象とならない場合もありますので、まずはご連絡ください。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
【ホームページアドレス】
トップページ中央の「分野別から探す」の「市民活動/地域・国際交流」内の「市民活動」をクリック。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
====================
#07:市制施行70周年事業
小田原デジタルアーカイブがスタートします
====================
問 広報広聴室 電話0465-33-1263
貴重な写真や映像、歴史的資料などを保存・整理・活用していきます
家の大掃除をしたとき、部屋の片隅からふっと出てきた1冊の古いアルバム。子どもの頃の家族写真、懐かしいまちの風景…。古いアルバムが伝える思い出は、誰にとっても大切な宝物です。
市制施行から70年を迎えた市では、そうした宝物が、時の流れとともに人々の記憶から薄れてしまわないようにするため、「小田原デジタルアーカイブ」に取り組んでいきます。
「小田原デジタルアーカイブ」とは
時代の移り変わりとともに、この小田原も姿を変えてきましたが、その時々に生きた人々の姿や生活、風景、まちなみなどは、今もなお私たちの心に深く刻まれています。そうした小田原の記憶とも言える貴重な写真や映像、歴史的資料などを、市民の皆さんや民間事業者の皆さん、行政などから継続的に広く収集し、デジタル化して保存・整理していくことで、劣化・散逸・消滅の危機から守り、"小田原の未来"へと引き継いでいこうとするものです。
収集した資料は、ホームページや広報紙などを使って市民の皆さんと共有し、ふるさとへの思いや地域のきずなを再認識するとともに、小田原の魅力を市内外に広く情報発信していきます。
--------------------
募集!小田原の歴史を物語る写真
--------------------
事業の開始に当たり、市民の皆さんから写真を募集します。写真にまつわるコメントなどとともにお寄せください。
[1]募集素材
「写真」(デジタル写真またはプリント写真)
[2]募集テーマ
「昔の小田原」または「将来に残したい小田原」(風景、まちなみ、四季折々の自然、建物、市民の生活・文化、地域のお祭りなど)
[3]活用方法
○お寄せいただいた写真は、事業の基礎資料とします。
○写真は広報広聴室で選定のうえ、来年度以降、市ホームページ上での公開を予定しています。また、広報紙や刊行物などに掲載させていただく場合があります。
[4]応募方法
メール、電子申請、広報広聴室に直接持参または郵送してください。
※応募方法や注意事項など詳しい内容については、市役所、支所・連絡所または市ホームページにある募集要領を必ずご確認ください。
====================
#08:おだわら情報
====================
--------------------
「もう一度、火の用心」
歳末火災特別警戒 12月26日日曜日〜31日金曜日
--------------------
問 警防課 電話0465-49-4421
寒さが厳しくなり、暖房器具を使うことが多くなるこの季節。慌ただしくなると、火の始末がおろそかになり、火災の危険性が高まります。
歳末火災特別警戒では、市消防本部、消防署、消防団が、警戒・警備体制を強化し、大型店舗などの特別査察、皆さんの防火意識を高めるための広報活動などを行います。
●空気が乾燥していますので、火の取り扱いには十分注意してください。
●火災を起こさないことはもちろんですが、放火されない環境づくりにも心掛け、火災のない明るい新年を迎えましょう。
--------------------
ご利用ください
〜公的個人認証サービスの電子証明書発行・更新の電話予約〜
--------------------
問・予約 市民窓口課 電話0465-33-1386
電子証明書の有効期間は3年です。電子証明書は所得税の電子申告に必要になります。確定申告直前は、更新などの手続きで窓口の混雑が予想されます。
証明書発行作業には20分前後かかるため、待ち時間を短縮し、速やかに手続きができるよう、電話予約をご利用ください。
※電子証明書の更新は、有効期限の3か月前からできます。
※予約をした場合でも、多少お待ちいただくことがあります。
※1日に取り扱いができる件数には限りがあります。
【手続きに必要なもの】
○住民基本台帳カード(更新のかたのみ)
○顔写真付きの公的な証明書(運転免許証、パスポートなど)
○手数料 500円
○住民基本台帳カード・電子証明書のパスワード
※ご不明な点はお問い合わせください。
--------------------
地震に備え、危険な塀を撤去しましょう
〜補助制度もあります〜
--------------------
問 防災対策課 電話0465-33-1855
地震は、いつどこで起こるか分かりません。現在、東海地震や神奈川県西部地震などの、大規模な地震の切迫性も指摘されています。道路沿いに多く見られるブロック塀は、地震などで倒壊し、人が下敷きになったり、避難や救助・消火活動の妨げとなることがあります。危険な塀をなくし、安全なまちづくりに努めましょう。
●危険な塀等撤去促進事業補助制度
市では、"危険な塀(※1)の撤去"や"生け垣への転換"に対して補助金を交付しています。工事前に必ずご相談ください。
補助対象
コンクリートブロックなどを用いて築造した塀または門柱で、道路(※2)面からの高さが1メートルを超えるものが対象です。
補助金額
○塀の撤去
道路に面する塀の長さ1メートルあたり8千円、上限20万円
○生け垣築造
道路に面する生け垣の長さ1メートルあたり6千円、上限15万円
・工事見積り額が補助金の額を下回る場合は、補助金額は工事見積り額になります。
・生け垣築造は、塀の撤去を伴う場合に限ります。
(※1)傾斜が著しい、風化、ひび割れなどが激しい塀。
(※2)国、県、市が管理する道路、建築基準法第42条に定める道路。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
<イベント中止のお知らせ>
おだわらいふ11月15日号14ページ中、12月8日水曜日に予定していた「子育てひろば おだっこ」は都合により中止になりました。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
--------------------
ヒルトン小田原リゾート&スパ
ジャパン・リーディング・リゾート賞を受賞
--------------------
問 企画政策課 電話0465-33-1379
ヒルトン小田原リゾート&スパは、2010年日本国内の最も優れたリゾートホテルに贈られるワールドトラベルアワードの『ジャパン・リーディング・リゾート賞』を受賞しました。
なお、ヒルトン小田原リゾート&スパは、2005年から4年連続でスパ部門の賞を受賞しています。
ワールドトラベルアワードとは全世界の旅行関連企業や個人の投票で決定される、最も名誉ある賞です。この機会に世界が認めたリゾートホテルを利用してみませんか。
--------------------
無事故で年末 笑顔で新年
12月11日土曜日〜20日月曜日は年末の交通事故防止運動
--------------------
問 暮らし安全課 電話0465-33-1396
■飲酒運転は犯罪です!!
年末年始は忘年会や新年会などで、飲酒の機会が多くなります。
飲酒にかかわる交通事故は、平成19年の道路交通法改正による厳罰化により、減少していますが、依然として小田原警察署管内でも発生しています。
飲酒運転は重大事故に直結する悪質・危険な犯罪です。一人一人が飲酒運転を絶対に「しない!」「させない!」という強い意志をもって、飲酒運転を根絶しましょう。
下堀自治会長 志村学さん
下堀自治会では、「地域の安全は地域で守る」を合い言葉に、平成18年5月から美化清掃を兼ねて、地域巡回パトロールを総勢41人で行っています。
平成21年4月からは、矢作小学校の児童の安全を守るため、毎日、12人のボランティアで挨拶運動もしながらの登校時の交通指導を行っています。
パトロールでは、その日の子どもたちのようすなどを日誌に記録し、ボランティア間で情報を共有しています。
地域内でのパトロール活動を通じて、顔見知りを増やすことで、地域の防犯力を高めていきたいと考えています。
また、同自治会では、都市計画道路「穴部国府津線」の開通を来年に控え、沿道開発など地域に大きな変化が予想されることから、将来を見据えた防犯や交通安全などを意識したまちづくりに地域で取り組んでいます。
====================
#09:無尽蔵プロジェクト
みかんの里からの贈り物「片浦みかんプロジェクト2010」始めました
====================
問 観光課 電話0465-33-1521
無尽蔵プロジェクトでは、小田原みかんの価値を高めるための「片浦みかんプロジェクト2010」がスタートしました。もぎたての旬の「早生みかん」をオリジナルのパッケージに詰め、その価値と美味しさをアピールします。
■片浦みかんのブランド化を目指して
かまぼこや梅干しなどと同様に、この地域を代表する名産品である「みかん」。しかし現状は、後継者不足や、採算性などの問題から生産量は激減し、その将来が懸念されています。
そこで、無尽蔵プロジェクト「小田原スタイルの情報発信」の取り組みとして、小田原みかんの価値を高めるため、まずは片浦地区で、みかんプロジェクトがスタートしました。
みかんの里として名を馳せた小田原みかんのブランド化を目指し、生産から流通までを一括化することで、みかん農家のかたがたにも利益をもたらし、みかん産業を再構築します。また販売価格の一部は『報徳推譲金』として積み立て、まちづくりのために役立てます。
■地元にも出回らない、みかんの味
今、片浦みかんは、地元の小田原でさえ、なかなか目にすることはできません。それは生産量がたいへん少ないためです。市場に出回るには、流通するだけの量が必要になりますが、狭くて急傾斜地という片浦地区の立地条件と、おいしいみかんができる標高や日照条件などを考えると、これ以上の増産はできないのです。だからこそ希少価値があり、おいしいことを知っている人だけに、箱詰めされて直接届けられてきました。
片浦みかんは、限られた人だけが楽しむ、おいしい冬の味覚になっていたのです。
ところが、その貴重な片浦みかんも、みかん農家のかたがたの高齢化と後継者不足により、毎年みかん畑が減少しつつあります。このままでは近い将来、片浦みかんは姿を消してしまうかもしれません。そこで、この貴重なおいしいみかんを後世に残すために、「ブランド化」をすることが必要なのです。
この「片浦みかんプロジェクト」が軌道に乗れば、片浦以外のみかんや、キウイなど、ほかの果物にも枠を広げ、「小田原柑橘倶楽部」として市内全域に取り組みを広げたいと考えています。
ぜひ、おいしい小田原の旬のみかんを味わってみてください。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
片浦みかんプロジェクト実行委員会事務局 電話0465-43-9039
ホームページ http://kataura-mikan.ninomiya.or.jp/
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
====================
#10:〈連載〉市民力
====================
心をつなぐ絵手紙の魅力 高橋浩子さん
「ヘタでいい、ヘタがいい」
市内いくつかの小学校のほか、大人を対象とした講座や、展示会などで絵手紙の魅力を伝えている高橋浩子さん。12月16日には、国府津小学校5年生の「親子レクリエーション」にボランティア講師として出向く予定です。子どもたちには、年賀状を手作りする楽しさを味わってほしいと言います。
最近は、パソコンや携帯電話のメールが便利となった一方で、自分の思いを自分の手作りのもので伝える機会が減っています。個性にあふれ、世界に1枚しかない、貴重な絵手紙。大切なのは、うまく書くことではありません。「ヘタでいい、ヘタがいい」どれだけ相手に気持ちを伝えられるかが、重要です。
「書いたら必ずポストに入れて、大切な人に思いを伝えましょう」サマースクールで暑中はがき作りをした際などに、高橋さんがそう言うと、離れて暮らす祖父母へ送るという子どもが多かったそうです。
10年ほど前に、仕事を辞めたとき、友人の勧めもあり、日本絵手紙協会の講座を受講。その後、以前から慣れ親しんでいた卓球仲間に、絵手紙を広げたところから、いろいろな場で、たくさんの人と絵手紙を楽しむ機会が増えました。絵手紙は、気持ちを送り、伝える手段。高橋さんが絵手紙の魅力を広めることで、さらに多くの人たちの、温かく優しい思いが、それぞれの大切な人に届きます。
====================
#11:〈連載〉尊徳道歌のこころ〈12〉(最終回)
====================
生かされていない「もの」を生かす
問 尊徳記念館 電話0465-36-2381
昔より 人の捨てざる なき物を
ひろひ集めて 民にあたへむ
二宮尊徳がその教えを分かりやすく詠み上げた道歌は、現代の私たちが尊徳の教えを知るうえでも、確かな道しるべとなるものです。ここでは、そのうちのいくつかを連載で紹介します。
この歌の「人の捨てざる」について、尊徳の上司に当たる山内薫正という人が「『人の捨てたる』というべきだ」と言ったところ、尊徳は「『捨てたる』とすれば、捨てなければ拾えないことになり、意味が狭くなる。また、捨てた物を拾うのは僧侶の道で、私の道ではない」と答えました。そして「人の捨てざる なき物」について、次のように説明しています。
「世の中には、人が捨てない物で、しかも無い物(生かされていない「もの」)はたいへん多い。第一に荒地、第二に借金の雑費とひまつぶし、第三に富む者のぜいたく、第四に貧しい者の怠けなどです。荒地などは捨てた土地のようですが、だれかが切り拓こうとすると、必ず持ち主がいて手が付けられません。だからこれは無い物であって捨てた物ではありません。また、借金の利息、借り換えなどの雑費も同じで、捨てた物ではなく無い物です。このほか富む者のぜいたくのための費用や貧しい者が怠けるための費用も同じです。
世の中にはこのように、捨てたのではなく無いも同然のものはいくらでもあるでしょう。こういう物を拾い集めて国家を建て直すもとにすれば、人々を多く救い、なお余裕があるはずです。人が捨てず、しかも無い物(生かされていない「もの」)を拾い集めるのは、私は幼い頃から努めてきた道で、今に至ったもとです。だからよく注意して集めて、世の中を救わなくてはなりません」(『二宮翁夜話』)。
生かされていない「もの」を生かす。それは「報徳仕法」を行ううえで、最も根本的な考え方でした。
※協力 報徳博物館館長代理 齋藤清一郎さん
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
8月〜11月号の記事の副題に誤りがありました。おわびして訂正します。(8月号の「至誠」→削除/9・10月号の「『至誠』−相手の立場に立って物事を考える」→削除/11月号の「『徳』に報いる道」→「先を見通して備える」)
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
====================
#12:いつまでも安心でおいしい水を届けるために!!
〜水道事業の現状と課題〜
====================
問 営業課 電話0465-41-1202
「水道事業」は、税金などで賄われる市の一般会計の事業とは異なり、水道を利用する皆さんの水道料金などによる、独立採算制の地方公営企業として運営されています。
ここでは市の「水道事業」が置かれている"現状"と、"課題"をお知らせします。
[現状]水道事業の財政(平成21年度の決算報告)
平成21年度決算では、純利益は約8,900万円となり、前年度の約4,200万円と比較して、およそ2倍となりました。これは、料金収入の減少以上に、経費を削減するなど、支出の抑制に努めた結果です。
一方で、市の水道事業ではこれまでに借り入れた企業債の残高が約117億2,100万円もあり、健全経営を行っていくうえでこれ以上借入金を増やすことは望ましくありません。しかし、借り入れをしなければ、施設の耐震化や老朽管の更新といった重要な事業を行うための財源が確保できないという、厳しい状況に置かれています。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
平成21年度決算
[収益的収支]
水道水を、家庭に送り届けるまでの財源と経費。
主な収入は皆さんの水道料金です。
○収入 28億2,400万円
・水道料金 25億6,100万円
・その他 2億6,300万円
○支出 27億3,500万円
・支払利息 4億500万円 国などからの借入金の利息
・経常経費 13億200万円 取水した水を浄水し、家庭へ水道水を届けるための施設の維持管理、人件費など
・減価償却費 10億2,800万円 水道の施設などを耐用年数に応じて各年度ごとに必要経費として計上する費用
・純利益 8,900万円 純利益は、翌年度以降の施設の建設や企業債償還の財源として積み立てられ、将来のために計画的に使われます。
[資本的収支]
水道施設の建設、水道管の布設などに必要な財源と経費。
主な収入は国などからの借入金や補助金です。
○収入 5億8,100万円
・企業債 4億5,000万円 水道施設の整備のための、国などからの借入金
・補助金など 1億3,100万円 一般会計や国からの補助金など
・不足分 10億8,000万円 不足分は、これまでの純利益などで補てんしました。
○支出 16億6,100万円
・建設改良費 10億3,100万円 水道施設の建設や修繕、水道管の布設や改良などの事業費
・企業債償還金 6億3,000万円 国などからの借入金の元金返済金
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
課題1 待ったなし!水道施設の整備
本市の水道管の総延長は約746キロメートルです。
鉄道でいうと、JR小田原駅から広島県尾道駅までの線路の長さに相当します。
このうち、国の耐震基準を満たしているのは約25パーセントで、耐震化が緊急の課題となっています。
また、浄水場や配水池などの耐震補強や、老朽化した水道管の更新も必要です。これには、平成21年度から10年間で総事業費が約128億円と見込まれており、この財源をどう捻出するかが課題となっています。
課題2 減り続ける料金収入
水道事業収入の根幹である水道料金収入は、皆さんの節水意識の向上や企業の経費節減などにより、平成7年度以降、減少し続けています。純利益についても、同様に減少傾向にあります。
また、平成17年度以降は、販売単価が製造原価を下回る「原価割れ」の状態となっており、採算が取れない状況が続いています。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
[平成7年度]→[平成21年度]
水道料金 34億2,400万円→25億6,100万円
純利益 6億6,800万円→8,900万円
1立方メートル当たりの販売単価(A) 140.28円→122.85円
1立方メートル当たりの製造原価(B) 126.92円→128.98円
差し引き(A-B) 13.36円→-6.13円
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
--------------------
水道水って…高い? 安い?
--------------------
ふだん水道水を使っていても、そのときの水道料金は分かりにくいものです。そこで、水道料金を身近なものに置き換えてみましょう。
市の水道水1立方メートル当たりの平均水道料金は約123円です。これを500ミリリットルのペットボトルに換算すると1本の値段は約0.06円です。
また、300リットルのお風呂をいっぱいにするには、36.9円かかる計算になります。
--------------------
安心でおいしい水を届けるために
〜安定経営のために欠かせない料金改定〜
--------------------
このような課題を解決していくため、水道局では業務の民間委託化や経費削減などの経営努力をしてきました。
しかし、今後、必要な施設更新のための事業費と将来の水道料金収入の見通しを考慮すると、健全経営が困難になることが見込まれます。
そこで、水道事業経営の健全性を確保するため、平成21年8月に「小田原市水道料金審議会」を設置し、議論してきました。この中で、「水道事業が置かれている状況から判断すると、水道水の安定供給のためには、水道料金の値上げはやむを得ない」とする答申が、平成22年3月に出されました。
皆さんに、いつまでも安心でおいしい水をお届けするための、財源の確保が急務となっています。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
【ホームページ】
トップページ中央の「分野別から探す」の「暮らし・環境」内の「水道」をクリック。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
====================
#13:〈連載〉あの日 あのとき 小田原
====================
第9回
市制施行から70年という節目の今年。
先人の営みより継承されたもの、自然事象とともに刻んだ足跡、古きよき故郷の懐かしい面影など、小田原の歴史には「無尽蔵の市民力」へとつながることがたくさんあります。
ここでは、そうした記録と記憶をたどります。
こども文化博覧会の楽しかった思い出
市制10周年記念事業
小田原こども文化博覧会
市制10周年を迎えた1950年「将来を担う子どもたちが、夢と希望を失わないように」「楽しく、面白く、ためになる子どものための博覧会を」という思いの皆さんが尽力し、城址公園を会場に「小田原こども文化博覧会」が開催されました。
象のウメ子
昨年9月に亡くなった、小田原のアイドルだった象のウメ子は、この「小田原こども文化博覧会」をきっかけに、タイからはるばるやって来ました。それから、59年もの間、小田原を見守ってくれていたのです。来園当時は体長127センチメートルの小さな象でした。
夢と希望を運ぶ博覧会
ゆうびん館、でんしん・でんわ館や観光館、産業館、野外劇場などが建設された城址公園。当時の鈴木十郎市長は、開会の挨拶の中で「…科学、芸術、産業、娯楽などの世界に対する子どもさんがたのあこがれを満たし、知識と教養の泉となり得ることを信じて疑いません」と博覧会への期待を述べました。
また、当時の広報紙には「関東地方で初の文化博覧会には、遠方からお客様が小田原に来る。ほこりっぽい道路に水をまいて、すがすがしい気持ちでお迎えしよう」という市民の声が掲載されています。博覧会を待ちわびた市民の、子どもたちや小田原に対する温かい思いをかいま見ることができます。
--------------------
表紙の言葉
「飯泉観音」
小田原ふるさとの原風景百選 No.68
--------------------
飯泉山勝福寺(飯泉観音)では12月17日・18日の2日間、関東地方で一番早いだるま市が開かれます。
境内にはだるまを売る露店が並び、商売繁盛、家内安全を願う人々で賑わいます。
====================
#14:市制70周年記念特集号
====================
平成22年12月、小田原市は、市制施行70周年を迎えます。これを記念して、12月19日日曜日には市民会館で、市勢発展にご尽力いただいたかたの「市制70周年表彰」などを行います。あわせて、小田原市制70周年記念事業市民実行委員会(木村秀昭会長)主催による、記念イベントも行われます。
問 総務課 電話0465-33-1291 広報広聴室 電話0465-33-1261
--------------------
70周年記念イベント
--------------------
期日:12月19日日曜日
場所:市民会館
※すべて観覧自由です。
■本館1〜3階
<展示等>
【時間】10:00〜18:00
●地場農産物や福祉団体手作りパンなどの即売
●小田原おでんカー
●「セピア色の写真展」
●小・中学生の「小田原の未来図」絵画展
●無尽蔵プロジェクトなどの作品展示や活動紹介
●相模人形芝居「下中座」公演(12:00〜13:00)
●小田原・懐かしのビデオ上映
■大ホール
<記念式典(功労表彰等)>
【時間】10:00〜11:30
<記念イベント>
【時間】14:00〜16:00
●オープニング 小田原北條太鼓
●柳家三三師匠
●小田原少年少女合唱隊
●オダワラのチカラ! The Movie
●未来を語る パネルディスカッション
(白井貴子さん、市内高校生、加藤市長ほか)
●ODAWARA えっさホイおどり
(総おどり)
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
みんなで祝う市制70周年
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
市制70周年記念事業
市民実行委員会 委員
永田 浩一さん
今年70歳になる小田原市。その「誕生会」を、たくさんのかたとお祝いしようと、さまざまな知恵を出し合ってきました。
イベントのタイトルはその名も「オダワラのチカラ」。このまちが持つ1つ1つの力を見つめ直し、結集することで、来場者にも主催者になってもらえるような、今までにない市民参加型の記念イベントにしていきます。
この地に根付いた伝統や歴史を大切にしながらも、そこから生まれてくるもの、産業や芸術など、これからの小田原を支える虹色の芽が、このイベントを通して生まれ、成長し、小田原を支える柱となってくれたらと期待しています。
新しいオダワラのチカラ…それは皆さんの中にあります。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
市民実行委員会ブログ http://70odawara.jp
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
「市民みんなが参加」をコンセプトに市民実行委員会では市制70周年記念事業ブログを開設しています。このブログでは、委員会が主催するイベント内容を発信していきます。また、コメントを書き込むことができますので、会場に行けないかたもぜひブログを活用し、参加してください。
--------------------
年表からひもとくおだわら70年の道のり
--------------------
市制施行から現在に至るまでの歴史。
私たちの心の中には、それぞれの小田原の思い出があります。
小田原が歩んできた70年を写真と年表で振り返ります。
1940(昭和15)年
●小田原町・足柄町・大窪村・早川村・酒匂村の一部が合併して小田原市となる
1948(昭和23)年
●下府中村と合併
1949(昭和24)年
●小田原競輪が始まる
1950(昭和25)年
●桜井村と合併
●こども文化博覧会開催
●こども遊園地・動物園開園
1954(昭和29)年
●豊川村・酒匂町・国府津町・上府中村・下曽我村・片浦村と合併
1955(昭和30)年
●郷土文化館、城山庭球場、城山陸上競技場完成
●「第10回国民体育大会」で本市が軟式庭球、ソフトボール競技の会場に
1956(昭和31)年
●曽我村の一部が分村合併
1958(昭和33)年
●市立病院開業
1960(昭和35)年
●小田原城天守閣完成
1962(昭和37)年
●市民会館開館
●市連合自治会(現:自治会総連合)が組織される
1964(昭和39)年
●東海道新幹線小田原駅開業
1969(昭和44)年
●第1回小田原市小学校体育大会開催
●小田原市文化団体連絡協議会発足
1970(昭和45)年
●御幸の浜プールオープン
1971(昭和46)年
●橘町と合併
●小田原城常盤木門完成
1976(昭和51)年
●荻窪に市役所庁舎完成
1980(昭和55)年
●中央公民館(現:生涯学習センターけやき)完成
●小田原市高齢者生きがい事業団(現:社団法人シルバー人材センター)発足
●栃木県今市市(現:日光市)と姉妹都市提携を結ぶ
1981(昭和56)年
●アメリカ合衆国カリフォルニア州チュラビスタ市と海外姉妹都市提携を結ぶ
1982(昭和57)年
●いこいの森オープン
1988(昭和63)年
●尊徳記念館、保健センターオープン
1989(平成元)年
●小田原北條太鼓の会結成
1990(平成2) 年
●「ときめき小田原夢まつり」開催
●石垣山一夜城歴史公園、辻村植物公園、小田原球場オープン
1991(平成3) 年
●ときめき国際学校スタート
●第1回クリーンさかわ実施
1992(平成4) 年
●生きがいふれあいセンターいそしぎオープン
1993(平成5) 年
●第1回市民ロビーコンサート開催
1994(平成6) 年
●「シルバー大学」開講
●かもめ図書館、小田原文学館オープン
●新消防本部庁舎完成
●小田原ケーブルテレビ開局
●第1回少年少女オーシャンクルーズ実施
1995(平成7) 年
●県立生命の星・地球博物館、小田原フラワーガーデンオープン
1996(平成8) 年
●川東タウンセンターマロニエ、鴨宮ケアセンターオープン
1997(平成9) 年
●小田原アリーナ、小田原テニスガーデンオープン
1998(平成10)年
●小田原城銅門、歴史見聞館、白秋童謡館オープン
●「第53回国民体育大会」で本市がバスケットボール、ソフトテニス、ソフトボール競技の会場に
1999(平成11)年
●第1回城下町おだわらツーデーマーチ開催
2000(平成12)年
●全国で初めて特例市に移行
2001(平成13)年
●市民活動サポートセンター、松永記念館老欅荘、小田原宿なりわい交流館オープン
2003(平成15)年
●小田原駅東西自由連絡通路「アークロード」開通
2004(平成16)年
●ヒルトン小田原リゾート&スパ、高校生チャレンジショップオープン
2005(平成17)年
●城北タウンセンターいずみオープン
●小田原映画祭シネマトピア2005、第1回サポセン祭り「は・に・わ」開催
2006(平成18)年
●小田原ふるさとの原風景百選決まる
2007(平成19)年
●コミュニティ放送局・FMおだわら開局
●橘タウンセンターこゆるぎオープン
●第1回小田原城ミュージックストリート開催
2009(平成21)年
●おだわらTRYフォーラム開催
●象のウメ子死亡
●事業仕分け実施
●無尽蔵プロジェクトスタート
2010(平成22)年
●片浦中学校閉校
●わんぱくらんど全面オープン
●地域別計画完成
●ふるさと食の祭典(全国丼サミットおだわら2010D7など)開催
--------------------
「あの頃の小田原」「今の小田原」「未来の小田原」
--------------------
今から20年前、30年前…あなたは何をしていましたか。
そのとき、現在の小田原にどのような夢を描いていましたか。
当時、「未来の小田原」への思いをつづったお二人に、ふるさと小田原について語っていただきました。
70周年の節目に、あなたにとっての、「あの頃の小田原」「今の小田原」「未来の小田原」を考えてみませんか。
70年間の市のあゆみ。
その軌跡をたどると、そこには人々の営みがありました。
そして、これからの小田原をつくり、支えていくのは、
市民の皆さんの力です。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
市制40周年記念作文コンクール
「甥の日記より 2010年12月20日」で市長賞を受賞
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
山崎 雅史さん 川崎市麻生区在住
「市制70周年の式典に水素自動車で…」30年前、現在の小田原を夢のような近未来都市として語った、山崎さん。
「中学生ながら、理想とする都市基盤の整備や広域行政の在り方について真剣に思い描いたことが評価され、うれしかったです。今の小田原の、景観に配慮した、自然と調和したまちなみや、地震に強いまちづくりなどの充実は素晴らしいですね」と、当時の作文を振り返る山崎さんの言葉には、ふるさとへの愛情に満ちあふれていました。
大学卒業と同時に、小田原を離れ、約20年。おかげで、小田原のことを外から客観的に見られるようになったといいます。
「小田原は首都圏と地方の『都市』のよいところを併せ持ち、いい意味で田舎の温かさがあります。その特徴を再認識することで、市民の皆さんには誇りを持ち続けていてほしいです」
「都市化とともに『個』が尊重される中にあっても、暮らしている人が協力し合い、地域が地域として機能できるような、温かさは何十年経っても絶対に失わないでほしいです」と、願いも込めてふるさとの将来像を語ります。
時代は流れ、まちの風景が変わっても、山崎さんにとって、今も変わらず小田原は大切なふるさとなのです。
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
市制50周年記念作文コンクール
「こんなまちに すみたいな」で市長賞を受賞
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
石井 華さん 茨城県つくば市在住
「たくさんの虫や動物と住めるまちになったらいいな…」20年前、人間と自然が共存していくまちづくりを、小学校1年生の純粋な気持ちでつづった石井さん。
久しぶりに里帰りしたこの日、小田原駅に近づく車窓に映った雄大な相模湾、箱根の山々や富士山が迎えてくれました。「あの頃と変わらない小田原の『原風景』に、地元へ帰ってきたワクワクや我が家の安らぎを感じます」と、瞳を輝かせます。
蛍やメダカが棲む小川、れんげの花が咲く田んぼのあぜ道、通学路のあじさいにかたつむり、今も変わらない小田原の自然が、石井さんのお気に入りでした。
学業や仕事の関係で小田原を離れて5年。酒匂川にはぐくまれたおいしい水、楽しかった小中学校の給食、便利で快適な交通網…。どこにでもあると思っていた幸せは、小田原ならではの貴重なものだったと気づき、感謝していると話します。
「中学3年生のとき、できたばかりの小田原テニスガーデンで試合をしたことや、暗くて細かった家の前の道が広く整備されたことなど、すべてが大切な思い出です。便利で快適なまちに進化しながらも、自然環境と調和したまちづくりを進めていってほしいですね」
小田原を離れたからこそ再確認できた「やっぱり小田原が好き」という気持ち、ふるさとへの思いは尽きません。
====================
まちづくり情報誌 小田原
毎月1日発行
No.1024
発行●小田原市 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 市役所総合案内 電話0465-33-1302
編集●広報広聴室 電話0465-33-1261・FAX0465-32-4640 〈C〉小田原市2010・11
9月1日現在 小田原市の人口198,554人 78,905世帯
広報おだわらは、資源保護のため再生紙を使用しています。
====================
