最終更新日:2013年02月27日
技人vol.7【製材工】大山謙司
柔軟に変化させるってことが必要だよね。
我が国における製材の歴史は古く、石器時代にまで遡(さかのぼ)ることができる。もっとも、この頃の鋸(のこぎり)といえるものは石槌(せきつち)製であり、生活に必要なものを加工する程度のものだったが、奈良時代には大木を大きな鋸で柱や板に加工する、大鋸挽(おがひき)が登場する。これが木挽(こびき)の始まりであり、現在の製材工の始まりでもある。江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎(かつしかほくさい)の富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)「遠江山中(とおとうみさんちゅう)」には、大
鋸(おが)で木を挽(ひ)く木挽のようすが富士を背景にして見事に描かれている。
明治に入ってようやく機械挽製材機が輸入されたが、それは水車を動力として丸ノコを回転させるという簡単なものだった。当時、木材を製材する場合、腹押し、鼻取り、ロクロ巻き、耳摺(す)り、長短切りと役割分担され、腹押しは、木材の切り口を腹に当て、鋸に向かって木材を送り、反対側では鼻取りが、挽き割られてくる木材を鳶口(とびぐち)や鎹(かすがい)を打ち込んで引っ張り、腹押しを助ける役目をしていた。動力はその後、火力から電気モーターへと変わってきた。
小田原の森は約4千ヘクタールで、かつて植樹した人工林が約6割を占める。これらの森林は、林業の担い手不足や木材の需要低迷のため森林の管理が行き届かず、手入れが不足した森林が大半である。以前は小田原城を中心に数多くの製材工が存在したが、木造建築の減少や一般住宅などへの国産材の需要減少に伴い、今は県西地域において数えるほどしか残っていない。
―今でも製材工程は分業化されているのですか?
腹で木材を押すっていうのは丸ノコで、僕も木工屋さんで見たことがあるんだけど、今では帯ノコが主流で、分業もほとんどなくなりましたね。ただ、山で製材するとかだと丸ノコを運んで製材するようだけど、今はトラックに載っけて簡単に移動できるし、現実に山で製材するって少ないんじゃないかな。
―今、大山さんはおいくつですか?
ちょうど60です。
―何代目になりますか?
木に携わって僕で三代目になるのかな。

一時保管場所に桟(さん)積みされた材木
―初代から製材工をされていたのですか?
初代はどっちかっていうと山だよね。山の伐採とかの仕事に携わっていて、二代目の僕の父が製材を始めたんです。
―小さい頃から製材所の中で育ってこられたとか?
そう。僕が小学校の頃、学校から帰ってきたら楽しいから送材車のハンドル回して行ったり来たりして、普通だったら「危ない」って怒られるんだろうけど、父は何も言わないのよ。だからいつも遊んだりしていて、いつの間にか自然とこの業界に入ったっていうか、カエルの子はカエルになっちゃったっていうかな。父は損した話もしてくれたけど、これだけ動くと今日一日これだけになったとか、その辺もうまく魅力を感じるように話してくれてたね。
―この仕事に就かれてもう何年ですか?
大学を出てからだから、もう38年になるね。授業のない日は配達とか家の手伝いをしていたし、どこかに就職しようという気もなかったしね。
―大山さんは製材工の仕事だけじゃなくて山の仕事もされているそうですが?
僕がやってるのは、よく知ってるところから頼まれて、小さな山の伐採仕事だけなんだけど、それ以上になるとまた業者がいるからね。僕は製材の方に目を向けてるんで、それに製材するところも市内では最近少ないでしょ。やっぱり、製材をするにも山の経験がないよりはあった方がいいよね。例えば、木ってのはさ、真っすぐなものばっかりじゃないから。こないだも加工依頼があって、もう1メートル上で切ってくれれば材が直材になったんだけどね。弓になってると製材のときにロスが出ちゃうんだよね。同じ4メートル採るにしても、伐採するときにもうちょっと曲がった部分を捨ててくれたら製材も楽だし、材も生きてくるもんね。

久野霊園より小田原市街を眺望する。山、海に囲まれた小田原は、資源の豊かさを実感する。
―木材に最初のノコを入れるときが一番難しいと伺いましたが?
お客さんに頼まれて賃加工っていうのをやるでしょ。それってお客さんの品物でしょ。そうなるとさ、失敗したらまずいし、この木からこういうものを採りたいってお客さんから言われてるわけだから、それを採れるようにしなきゃいけないしな。はじめに丸太を見たとき、ここが一番いいかなっていう見方はするよ。それでぐるっと見て、キズとか木の表面が膨らんでるところは昔何かあったとかさ、それから節の痕(あと)とか見て、それでここかなって、やっぱり最初にノコを入れる位置が一番難しいよね。
ある程度長方形とか半製品になってる場合は楽なんだけど、丸の原木でしょ。木には根っこの膨らみもあるし、上に行くと枝分かれしてるから木の股(また)ってのがあるんだけど、そこに下手にノコを入れると帯ノコが木の力で締められて止まっちゃうのよ。そんなとき楔(くさび)を入れたりとかすればそれ以上締まんないんだけど、木の素性によってはそこを攻めていかないといけないって場合もあるからね。だからこうしたらこうなるとか、一手か二手先は想像するよ。丸太を見ればおよその予測は立つけど、そういうのは自分で経験してさ、自然に身についてくるよね。面倒くさいとか思ったら駄目(だめ)だね。
―今でも最初にノコを入れるときは緊張されますか?

宮城野林道途中の手入れされた森。手入れされた森は、きれいな陽の光が地面に落ちる。
―小田原市の「*報徳の森プロジェクト」にも関わっておられるのですか?
僕、個人で公の仕事をっていうよりも、小田原地区木材協同組合っていう組織があるんですよ。そこを通して手伝わせてもらってるんですね。
*小田原の森の再生を図りつつ、森からの恵みや木材を活用して東日本大震災による被災地の復興を支援するプロジェクト。これまで相馬において、小田原材による直売所やパン屋さんの建築、産業再生のための復興ブランド食品の開発を支援してきている。
―地域材を使うと、どのようなメリットがありますか?
そのあたりがなかなか難しいと思うんだけども、以前は流通も今ほど発達してなかったから、地元の木で家を建てるのが普通だったけどさ、今はトラックで遠くからでも持ってこれるからね。
自分たちが生活している場所だから、昔に戻れっていうわけじゃないけど、もう一度近場に目を向けるってのかな、極端な話をすれば、地域材だったら木材の運搬費も少なくって済むわけだよね。だから、近くに材木があるんだったら近くの方がいいんじゃないかなってことだよね。
それとやっぱり地元に生えた木を地元で使うっていうのは、気候に合ってるし木も馴染(なじ)むしね。前に一度手伝わせてもらった仕事で、よそから木材がくるでしょ。そうするとね、早めに取り寄せて、こちらの気候に慣らすんですよ。温度や湿度が違うわけだからね。
それで大工さんが墨入れて使っていくわけだよね。現実、僕もよその材を仕入れてすぐに使ったけど、隙間(すきま)が空いちゃってさ、やっぱりそのとおりだった。
―山とか森に対してはどのようなメリットがありますか?
地域材を使うことによって、林業の活性化につながっていくし、そうすれば高い安いは別にしてお金も地元に落ちる。お金が落ちれば山も手入れするようになるし、人の交流も深まるとかね。いいことはいろいろあると思うんだけど、悲しいかな木材の値段が上がらないっていうのかな。40年、50年と時間のかかる中で、山の立木を売ってもなかなか思ったような金額にならないとかね。それがさ、ある程度の収入が得られれば、また山に植林して山に手が入ってくるんだけども、山を持ってる人の中でも、なかなかそこまでできる人ってのは少ないよね。昔だったらさ、山の木の枝なんかお風呂で燃やすとかにしてね。また、山に手が入ってくれば、魅力を感じてくれる人もいると思うんだけどね。
―今、小田原周辺の山ってどんな状態ですか?
根府川あたりから箱根の麓(ふもと)、久野あたりまでだと手の入ってる所もあるし、全然入ってない所もあるね。このあたりは林道整備とかできてるんだけど、林道に面してても手の入らない所もあるみたいよ。それはさっき言ったみたいに付加価値があんまりつかないでそれだったら放っておいた方がいいとかさ。そうなってくると木もある程度年数経ったら循環してやらないと、山も駄目(だめ)になっちゃうしね。
―昔と比べて大山さんが感じる変化ってありますか?
それに単価の競争になってきたし、大手は資金力があって外材とかまとめて購入して単価を下げるとかしてるからさ、小田原の工務店さんも少量でもいいからもうちょっと地元のものを使ってくれるといいんだけどね。そうすると山だってきれいになるんじゃないのかな。
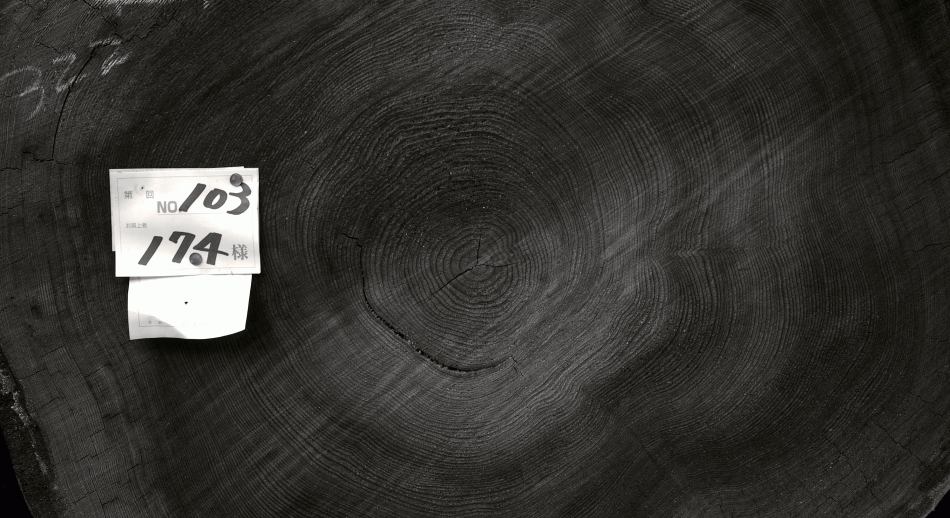
箱根の関所付近で伐採された杉の大木、樹齢約400年

宮城野林道途中の手入れされた森。手入れされた森は、きれいな陽の光が地面に落ちる。
小田原地区で一番多いときは58社あったのかな。今は23社、半分以下だよね。仲間が減るってのはあまりよくないんだよね。昔はそれだけ軒数があってもやっていけたんだもんね。注文の場合は別だけど、製材しててもこの丸太はこれにしか使えないっていう先入観を捨てて、どんな注文にでもなるべく変化できるよう工夫はしてるよね。
―変化させやすい材木を作るということは具体的にどのようなことをいうのですか?
たとえばこの面がよさそうだからって最初ノコを入れてね、よければそれで形を取っていこうと、もう一つよくないなと思ったら、ちょっと予定変更して、それでよければ4.5センチの厚みにするところを倍にして長方形の材にして、そうするとそれに近いサイズの注文があればそれで出せるし、駄目(だめ)だったらそれを半分にして板状にして販売できるとか、そういうふうに変化できるような商品にするってことだよね。僕はいろいろな注文にすぐ対応できるようにしてストックしてるけどね。今も丸太を1本寝かしてるけど、それもやっぱり変化できるように考えてるね。商品になるまでまだ時間がかかるし、先行投資も必要だけど、変化できるような投資じゃないとね。
―製材工として38年ですが当初からそのようなお考えでしたか?
先代がそういう感性だったんだな。やっぱり変化できるようなやり方、目で見て手で触って、これはこういうふうにした方がって自然に身についてきたよな。すぐ右から左に動く商品じゃないだけに僕もそういうの引き継いだっていうか、柔軟に考えないと材も生きてこないしね。ちょっと極端な話だけど、既製品で売っているような商品はあまり作んないのよ。そういうのは問屋さんとかに行けばいっぱいあるからさ。
―大山さんはどのようになれば理想的だとお考えですか?
住宅に限らず適材適所でうまく利用してくれればいいと思うんだけど、せっかくあるものをさ、指くわえて見てるんじゃなくて、そこで何か行動して、アピールしてもう少し消費者の方にも目を向けてもらえるようにしていかないとね。昔は大工さんもノミやノコで柱や梁(はり)に穴を開けたりしていたけど、今はプレカットっていって機械で一括して開けてくれるような工場もできたから、梁や柱、土台などの躯(く)体は工場で探してくれるんだよね。こっちからそこに材木を送るって方法もあるけども、向うで全部やってくれるからね。材木をオーダーしてることには変わりないんだけど、仕入れルートとかが変わってくるからね。大工さんが自分で木を刻んでくれればさ、問屋から買わなくても小田原の木材でも可能だもんね。そしたらさ、遠方から運んでくる横持ちの運賃なんかいらないしね。何かもっと活性化できればいいなって思うんだけどもね。
僕なんかでも少しでも高く買ってもらいたいという気持ちもあるけども、そこを抑えて商品が流れればいいと思うし、それじゃないとせっかく地元に木があってもさ、値段が飛び抜けてたら使おうと思っても、それだったら別の木にするなんてことになってしまうからね。そのあたりはこれからの課題になっていくとは思うんだけど、まだ木にこだわってくれている人がいる間はさ、なるべく価格差がないようにもっていかないと、今はそんな考え方でいるんだけどね。それから後、乾燥。これがネックになってくるんですよ。僕自身は天然乾燥がベターだと思ってるんだけど、それだとある程度保管しないといけないし、そうすると保管場所が必要になってくるし、資金力の問題も絡んでくるからね。
―大山さんから何かご提言はありますか?
ものづくりには裏方ってのが絶対必要だし、俺が俺がじゃなくてさ、ものづくりって人に喜びを与えるだとかさ、顔が見えてれば安心感が持てるとか、それでお客さんとこうやって話ができたとかね。前だけど工務店さんが木の伐採を森林組合に頼んで、森林組合で木を用意して、それをお客さんが伐採からついて行って、伐採が終わったらトラックで木材を製材工場に持ってきて。それで僕がこれはその家のこういった所に使うってことで製材して、丸が四角になったりとか、お客さんが目の前で見てるからね。いろんな人の手を経てものが動いていくのを見るっていう、そういう経験もいいと思うんだよね。
僕は取り巻きっていうの、周りを大事にしたいし、お世話になってるっていう気持ちがあるもんで、関わり合ってやっていけたらいいなって。今は仲間作りをしていかないとなかなか難しいよね。
―大山さんにとって製材の面白さってどのあたりにあるんですか?
やっぱり変化できるってことかな。それにいいものが採れたときとか、それでお客さんに喜んでもらえればそれが一番最高だよな。前に、親が庭に銀杏(いちょう)の木を植えて、それで亡くなられてその木を切ったって、70センチか80センチくらいの丸太を車のトランクに入れて埼玉からお客さんが持って来られてさ、それをすぐに製材して、プレナーって仕上げまでする機械があったもんで仕上げたら、親への想(おも)いがその人にはあるみたいでさ、喜んでくれて、どこかの酒屋に行って後で酒一升買って届けてくれたよ。親の遺(のこ)してくれたものを自分たちでうまく使えるっていうの、その安心感ていうか想(おも)いが次の世代につながっていくっていうかさ、そういうのっていいよな。
―木材に関わる仕事に就かれる方は年々減っているのですか?
親子でね、やってるところはやってるけどね、次の代に渡せないでやめちゃうとか。僕なんかも先輩には「大山、産地に任しとけばやってくれるんだから、もう製材なんかやめちまいな」ってよく言われたよ。でもね、そうもいかないんだよ。自分の機械があるんだから、それだったら量はできないけど、ある程度加工はできるんだから、自分でやった方が早いし、それに遠くまで行かなくてもいいしな。
僕らもね、次の世代に引き継ぎたいし、状況は難しくなってきているけど何か方法を見つけ出してほしいし、自分一人じゃ難しいかも知れないけど、周りを巻き込みながらうまく接点を作ってやっていってくれればいいなって、僕だけじゃなくて木に携わる人はみんなそう思ってる。僕らも365日製材やってるわけじゃないし、そんなに毎日仕事があるわけでもないし、仕事がないときは他の仕事をやるとか、木から外れないでね。そうすると生活の糧にもなるしね。

木を見上げる大山氏

製材中の大山氏
―製材工になろうと思うと何年ぐらいで一人前になれますか?
どうだろ、本気でやれば、5年くらいでおよそのことはできるようになるんじゃないかな。図面を見て何がどれだけ必要かって理解できなきゃしょうがないんだけど、できれば山から覚えていくのが一番いいんだろうね。
―製材は今後どのように変わっていきそうですか?
普通の住宅じゃなく特殊っていうか、そんな感じで推移していくんじゃないかな。このあたりは消費地なんで、なおさらそういう可能性はあるよな。だから普通の材木じゃなくて、変わった材木とかを求められるようになるんじゃないかな。普通の住宅に使う木材は産地に任せて、こちらはそれ以外の建物とか、サイズの変わったものとか、細かいところでお手伝いしていくっていうところじゃないかな。
―次の人生があるとしたら製材工に就かれますか?
どうだろうね、でも自然との関わりだから精神的な負担はないもんね。それに自己満足の世界に入れるところもあるし、そういった面ではいいかなって思うよね。人頼みじゃなくて、自分の手で触りながら自分で作ってるから比較的ストレスは少ないよね。ただ、もうちょっとゆとりが欲しいとは思うけどね。
「技人」
温暖な気候と豊かな資源、そして地理的な条件に恵まれたまち・小田原には、いにしえよりさまざまな「なりわい」が発達し、歴史と文化を彩り、人々の暮らしを豊かなものにしてきた「智恵」が今に伝えられています。本シリーズは、その姿と生きざまを多くの人に知っていただき、地域の豊かな文化を再構築するきっかけとなれば、との願いが込められています。
企画:地域資源発掘発信事業実行委員会
・小田原二世会
・小田原箱根商工会議所青年部
・小田原商店街連合会青年部
・(社)小田原青年会議所
・特定非営利活動法人 おだわらシネストピア
・特定非営利活動法人 小田原まちづくり応援団
・小田原市
編集:相模アーカイブス委員会
写真・文:林 久雄
発行:小田原市
問い合わせ:小田原市広報広聴課 事務局(0465-33-1261)
平成24年11月
本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部または全部について著作権者の
許諾を得ずに、無断で複写・複製することは禁じられています。
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室
電話番号:0465-33-1261
FAX番号:0465-32-4640

