小田原Lエール認定企業トップインタビュー
♯3 丹羽病院(医療法人社団 帰陽会)
取材日:令和7年1月28日
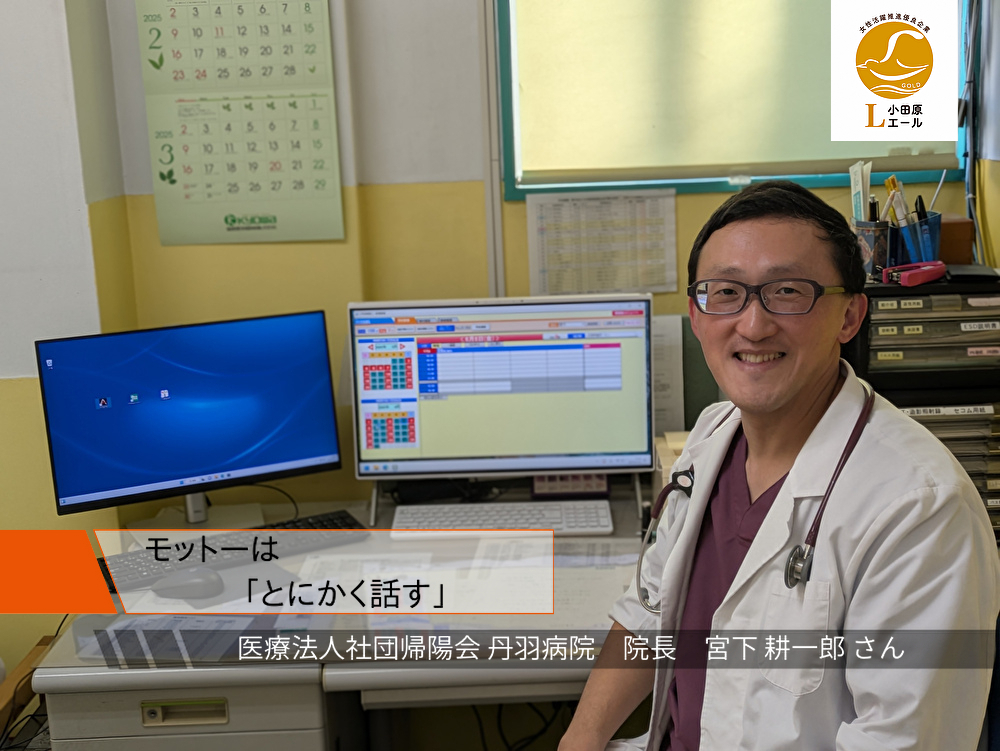
医療法人社団帰陽会さんは、地域医療、保健、福祉のネットワークの強化を目指し幅広く事業展開をしています。
その中心にあるのが丹羽病院です。
丹羽病院院長の宮下耕一郎さんにお話をお伺いしました。
企業情報
概要
- 小田原市荻窪406
- 消化器科・外科・内科・肛門科病院
- 従業員数208人(令和7年2月15日時点)
女性活躍の主な取組
- 小田原Lエールゴールドステージ認定企業
- 仕事と治療の両立を支援するため、不妊治療休暇制度を導入
- 女性の医師や、技師等を積極的に採用している
Episode1 女性専門の消化器外来開設と小田原Lエール
実はね、私達が小田原Lエールに出会ったのは偶然だったんですよ。 もともと「女性」という視点が重要ってずっと思ってきていたんですけど。 ここは病院なので、もちろん患者さんは性別問わずレスキューしなければならない。 すべての患者さんに、公平に平等に健康に触れていただきたいと思っているんです。 でも、女性は、消化器系の検査には少し積極的じゃない。検査の性格上、胃カメラならまだいいんですけど、大腸検査となると、ちょっと恥ずかしいとかそういう気持ちが出てしまって、受検率があまり高くないんですよね。
そこで、うちは消化器が専門ですから、昨年、女性専門の消化器外来を開設したんです。 これ、全国的にも結構珍しいと思うんですよね。治療はもちろんですけど、消化器系の健診と言うことです。健康であれば、仕事もプライベートも元気にやっていけるじゃないですか。 女性活躍にかかわる取組だと思うんです。 それで、いろいろ調べていたら、小田原市で取り組んでいる小田原Lエールに出会って。どんな取り組みしているのかな、うちの取組も役に立つかなと思って、申請して、ゴールド認定をいただいたんです。
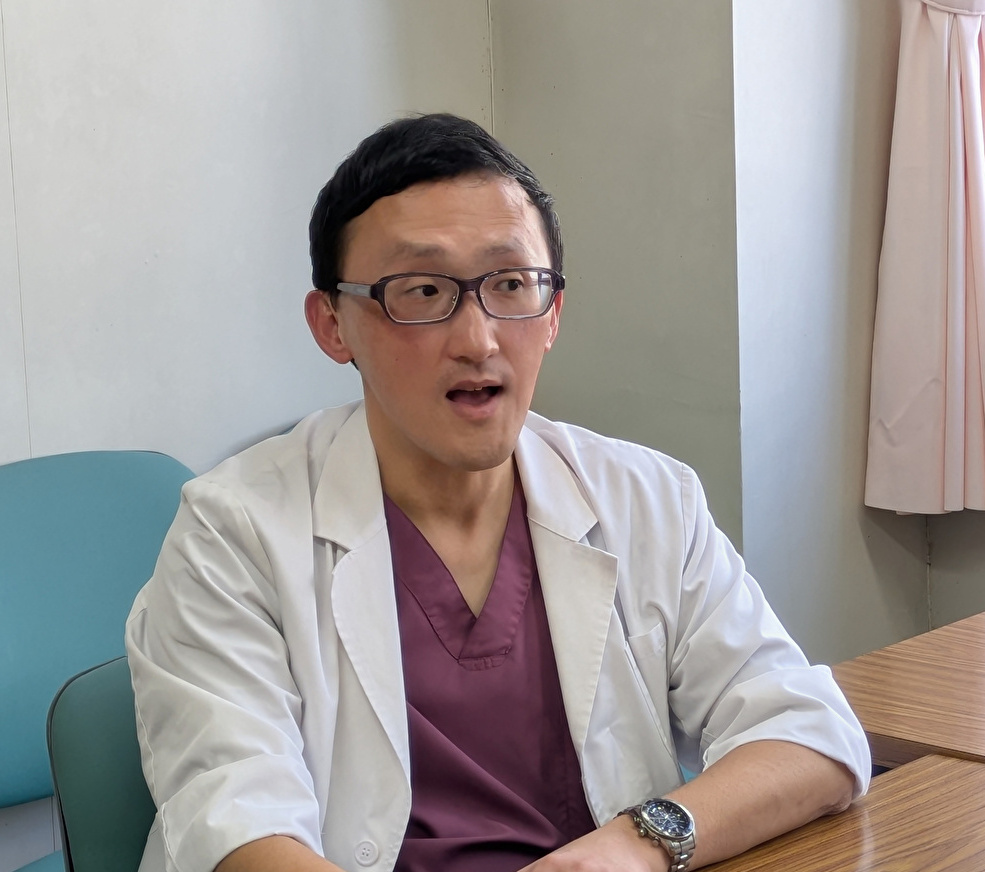
Episode2 とにかく話すこと
うちのスタッフのコミュニケーションはとても優秀だと思いますよ。 とにかく「話す」、これが大切だと思うんですよ。 私が、話し好きというのもあると思うんですけどね。 ちょっとしたことを、廊下ですれ違った時なんかでも「〇〇の件だけど、どう思う?」とか「ちょっとこのことについて話したいんだけど」とか、役職とか関係なく気軽に声をかけあっていると思うんです。 話すことは、お互いの体調なんかもわかるわけです。 「顔色良くないね、体調悪いの?」 こんな声かけも、簡単そうでなかなか難しですよね。 普段からコミュニケーションをとる風土があれば、スタッフの健康管理にも、業務のリスク管理にもつながりますよね。 よいことばかりです。 でもね、これが立ち話で終わっては意味がないと思うんですよ。つまり、この雰囲気というか、自由に話せるというのを、「会議」にも取り入れないと、組織は絶対に変わっていかないと思うんですよね。 もともと、女性が多い職場ですが、それでも、以前の運営会議のメンバーは男性ばかりだったんですよ。 でも、今は、運営会議メンバーの7割強が女性です。 積極的に発言してもらえています。
スタッフ同士のよいコミュニケーションは、患者さんにきちんと向き合うことにも繋がると思うんですよ。 うちの女性スタッフは、特に上手に患者さんに声掛けをしているので、男性スタッフも見習うところが多いですよ。
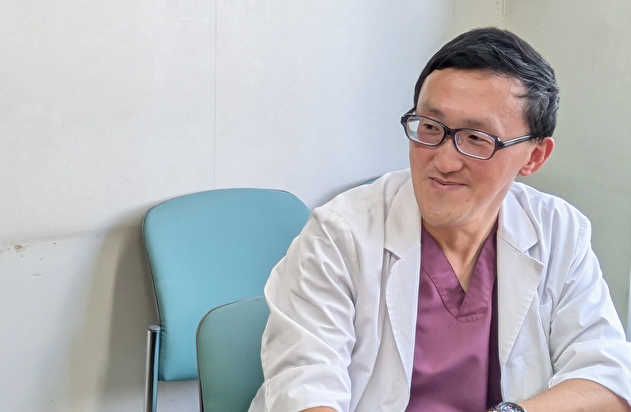
Episode3 制度を整え、制度を活用する
女性スタッフが多いですから、産休育休を取得する人は多いですね。 そして復帰してまた頑張ってくれています。 就業規則の見直しには力を入れています。 特徴的な取組として『子育て中のスタッフが、保育園からお迎えの要請を受けた時など5分以内に退勤するよう努める』と周知しています。 周知することが大切だと思っていて、そうすれば、すぐに退勤しやすいですし、周囲も支援しやすいですよね。
また、男性の医師が育休を取得しています。 男性であること、そして医師であることは、なんとなく育休を取得しにくいイメージないですか? でも、やればできるんです。患者さんにも事情をお話しています。もちろんご本人の承認を得てですが。 そうすると、患者さんも子育てを応援して下さり、「先生が帰ってくるまで、待っているよ」と言ってくださるんです。 もう一例。 先ほどお話した女性の消化器外来の担当医はもちろん女性です。 子育て中なので、診療時間なども少し変則的になっています。 患者さんにはご迷惑をおかけすることになりますけど、「先生、子育てしながら私たちを診てくれているんですね」と応援して下さるんですよ。
Episode4 新しいチャレンジ
次にやりたいこと、やらなくてはならないこととして、うちの取組や企業風土を市民の皆さんに知ってもらいたいんですよね。 スタッフと話しているのは、SNS配信です。医療の正しい情報も入れながら、紹介できたらいいなって思っています。 面白いでしょ。

スタッフの方にもお聞きしました

関野 江美 さん
働き方
私は、「臨床検査技師」という専門職として勤務しています。 この職場で、産休も育休もとって、子育てをしながら働いてきました。 もともとはパートでしたので、時短勤務にはしなかったんですけど、その都度職場と相談して、働き方を変えていったんです。 医療現場としては珍しく、先生方も柔軟な働き方をしているので、働き方を変えていくことにも、不安はなかったです。 上の子が小学校に入学するタイミングで、正職員になりました。 でも、まだ子どもが小さかったので残業はできませんでしたけど。 最初から、仕事をずっと続けるという意気込みがあったわけではないんです。 「やれるうちはやろう」とか、そんな感じでしたよ。 今となっては自分がこんなにできる・・・というか、こんなに長く続くとは思わなかったです。 子どもが小さい時は、急に保育園に迎えに行かなくてはならないことって多いですよね。 そういうことが続いてしまうと、やっぱり職場に迷惑をかけていると思っていました。 家族の協力はもちろんなんですけど、職場の皆さんが協力してくださったので、続けられたんじゃないかな。 具体的には、やっぱり声かけですかね。 「大丈夫よ」とか「子どもはどう?」とか、皆さんがいつも言ってくれたので。
常に改革!
これからの目標は、「常に改革」です。いざこざとかあってもいいんですよ、全然。いろいろな人が集まっているんだから、当たり前ですよね。でも、それをきちんとあとで振り返れるような、そんな職場にしたいです。変えられるところは変えて、常にみんなで同じ方向を見ていきたいです。常に改革っていうのはそういうイメージ。部下たちの意見も取り込んでやっていきたいって思います。今もそうしているつもりですが、これからも続けていきたいです。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
電話番号:0465-33-1725