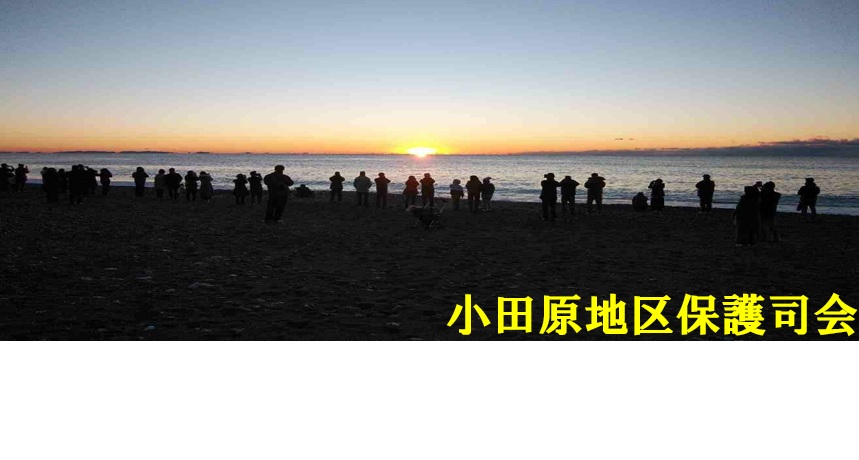
保護司とは
保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協働して、保護観察などに当たります。給与は支給されませんが、活動に沿った実費弁償金が支給されます。全国に約4万6000人います。
保護司の主な活動
《保護観察》
仮釈放が決まり保護観察対象(少年を含む)となった人と、月に1~2回面談しながら生活状況を把握した上で地域社会の中での立ち直りに向けて必要な指導をします。
《生活環境調整》
《犯罪予防活動》
犯罪や非行を生み出さない社会を作るためには、地域で暮らす人たちの更生保護に対する理解を広めていくことが大切です。そのため、行政や地域の関係団体、学校、警察などと連携を図りながら犯罪予防活動の啓発に努めており、更生保護に関する全国的な運動である「社会を明るくする運動」や再犯防止に向けた活動に協力しています。
【保護司とともにボランティア】
≪協力雇用主≫ ~「就労」と「見守り」の両方を担う~
犯罪や非行をした人の立ち直りには、働くことが大変重要です。協力雇用主は、犯罪や非行をした人の自立や社会復帰に協力することを目的として、彼らを雇用しようとする事業主です。全国に2万5000事業者がいます。
≪更生保護施設・自立準備ホーム≫ ~社会復帰する人の居場所をつくる~
刑務所などを出た後、住む場所がない人たちに宿泊場所や食事を提供し、自立に向けた支援等を行う民間の施設です。更生保護施設は約100施設あります。また、自立準備ホームは約500事業者が登録しています。
更生保護女性会は、地域の犯罪予防活動や更生支援を行う女性のボランティアです。非行問題を考えるミニ集会のほか、子育て支援活動など、多様な活動をしています。全国に約12万人います。
≪BBS会≫ ~若い人の視点で立ち直り支援に参加~
様々な問題を抱える少年たちと、兄や姉のように身近な立場で接することで、少年たちの成長を助ける青年ボランティアです。全国に約4500人います。
【第75回“社会を明るくする運動”】
毎年7月を強調月間として法務省が主体となり全国的に行われる犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える、生きづらさに寄り添う、「地域の力」の推進運動ですが、年間を通して活動しています。
「Time with Hope 進む、希望とともに」がメインコピーです。
がんばれるのは、どんなときだろう。 踏ん張れるのは、どんなときだろう。
自分を認めてくれる一言。 肩をたたく手の温かさ。 遠くから見守るそのまなざし。
待っている人の存在に気付いたとき、立ち直れると信じられる。
たとえ時間がかかっても。 進む、希望とともに。
【保護司体験談】 No.2
<やりがいを感じたひと時>
「お元気ですか。」とスーパーマーケットの駐車場で声を掛けられた。声の主はA君で、10年ぶりの再会でした。声を掛けられた時には、すぐにA君とは分かりませんでしたが、その面影からA君と思い出しました。A君は今、このスーパーマーケットの近くに家を建て、妻子と住み、当時就職した会社の工場で職長として働いているとのことでした。
思い起こせばA君は、当時中学生で、学校の窓ガラスを割ったり、駐車車両の上に乗ったりと仲間と暴れ回っていた非行少年でした。家には戻らず、不良仲間の家を転々としていました。警察に捕まり保護観察処分となり、私が担当保護司になりました。A君を家に戻し、進学先を話し合い、高校受験させ入学させることができました。ガソリンスタンド等でアルバイトをしながら通学していましたが、遊び癖が出てしまい、退学してしまったのです。
そして再び不良仲間の家を転々とする生活に戻ってしまいました。そんな時に面接で「働くとは」「家族団らんとは」「幸せとは」について話し合いました。その結果、A君は自宅に戻り、落ち着いて生活できるようになりました。3ヵ月ほどたったころに「そろそろ働いては」と言うと「働きたい」と意欲をみせました。父親の紹介で面接を受けることになりました。履歴書の書き方、面接時の姿勢・態度・返答の仕方を教え、最後にメモ用紙を持たせメモを取ることを勧めました。
結果、18人中3人の採用枠に合格したのです。決め手はメモだったそうです。製造ライン現場の仕事でメモを取りながら行っていたため、間違えがなく上司や仲間から信用を得ているようでした。初任給が思っていたより高額で喜んでいたので、生活費・小遣い・貯金に三分割して使うよう指導しました。保護観察終了時の面接には、今の若者らしい髪形・服装をして来て、開口一番「彼女ができた。工場事務所の職員で1歳年上で、彼女から声がかかって来た。」とのこと。また「彼女に預金通帳を取られた。」と嬉しそうに話してくれた。その彼女が今の奥さんとのこと。
A君の保護観察は5年を要しました。大変でしたが「やりがい」があったと振り返る
ことができ、駐車場での嬉しいひと時を過ごすことができました。
小田原地区保護司会
城山・城南・白鴎・白山・鴨宮・千代・城北・泉・国府津・橘・酒匂の11のブロックに分かれており、その地域ごとに活動しています。
| 会長 | 宮崎彰典 |
| 副会長 | 島津三喜子 神谷賢治 菊地淳 |
| 総務部会長 副部会長 会計・書記 |
菊地淳 菊地映江 島津三喜子 |
| 研修部会長 副部会長 |
神谷賢治 山崎由起子 朝倉義勝 |
| 協力組織部会長 副部会長 |
鈴木香 山地博 小島君予 |
| 犯罪予防部会長 副部会長 |
髙橋義雄 廣本まさ子 椎野正幸 |
| 広報部会長 副部会長 |
小林幸一 菴原和子 本多秋晴 |
| 相談役 | 大場得道 |
| 4月: | 総会、自主研修、広報「かけはし」発行 |
| 5月: | 新任保護司研修、役員研修 |
| 6月: | 地域別定例研修、ホームページ更新 |
| 7月: | “社会を明るくする運動”街頭宣伝・ホゴちゃん地域の集い |
| 8月: | 報徳更生寮清掃奉仕活動、かけはし講座 |
| 9月: | ホームページ更新 |
| 10月: | 地域別定例研修、新任保護司研修、広報「かけはし」発行 |
| 11月: | 全市一斉あいさつ運動、UMECO祭り、施設視察研修 |
| 12月: | ホームページ更新 |
| 1月: | 自主研修、新春の集い、受賞祝賀会 |
| 2月: | 地域別定例研修、更生保護女性会との交流会 |
| 3月: | ホームページの更新 |
【更生保護サポートセンター小田原】(小田原地区保護司会の事務所)
| 所 在 地 | 小田原市飯田岡117-3 |
| 連 絡 先 | 電話:0465-20-8425 FAX:0465-20-8645 |
| 開所日時 |
月・火・木・金 (10時から16時まで) 土・日 (9時から12時まで) |
| 閉 所 日 | 水曜、お盆、年末年始ほか |
保護司の活動に興味のある方は
小田原市で保護司をやってみたい方、保護司の活動に興味がある方は、地域の中で活躍している保護司や小田原地区保護司会(更生保護サポートセンター小田原)へ是非ご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:人権・男女共同参画課 人権・男女共同参画係
電話番号:0465-33-1725