第12章 太平洋戦争の前夜
「智恵子のこと、そろそろ考えてやらなければいけませんね」
ある夜、二人だけで落ち着いた時、ハナが言った。
「いくつになったかな」
「もう22ですわ」
「正直で、しっかりした者がほしいな、店をやってもらうんだから ― よし、方々へ頼んでみよう」
定五郎は、智恵子には婿をもらって、行く行くは東海商会をまかせることにしたいと考えていた。そういう心積もりでさて婿探しをやってみると、なかなか思うように行かない。侯補者はいくらでもあるのだが、やはり「帯に短かし―」 の言葉通りであった。
「あなたにはご親類が多いのだから、誰か身内の中で適当な方がいそうなもんですね。『灯台下暗し』ということもありますよ」
と言う人があった。
そう注意されてみると全くその通りで、今まで眼を外にばかり向けていたのにはじめて気付く定五郎であった。
「川瀬さんの勝さん、どうでしよう?」
ハナが言った。
「えっ、勝君 ― なるほどなぁ、あんまり身近かすぎるので気がつかなかったが、勝君はいいね ― だがくれるかしら・・・」
「勝さんなら気心も知れているし、立派な青年だし、わたしは似合いだと思うのですけど ― 」
「うん、勝君ならわたしも結構だ。じゃ一つ話してみるか」
勝は、定五郎にとってはいとこ同志の川瀬勝五郎の長男で、現在農園の仕事をやっている好青年であった。
元来、川瀬勝五郎の渡米は定五郎の呼び寄せによるもので、そんな関係から、勝五郎が飯屋をやり続いてホテルを経営、さらにその後農園にまで手をひろげて、長男勝、次男英夫を呼び寄せるようになった ― そのはじめから現在に至るまで、定五郎はいろいろ世話も焼いてきたし、また特に親しく往き来をしている間柄でもあった。
だから、勝が来てくれるというのであれば心にかかることは何一つないばかりか、第一気が楽で、将来きっとうまくやっていけると思えた。
定五郎は早速勝五郎のもとへこの縁談を申し込んだ。ところが、勝五郎の方では勝と智恵子の結婚には大賛成だが、長男だから婿にやるのは困る、こちらに来て貰いたいということだった。
定五郎もハナもはじめは可愛い智恵子を手ばなす気にはどうしてもなれなかったが、申し込まれた勝五郎の方がかえって熱心に是非貰いたいと言ってくるので、仲人の斡旋もあり、ついに智恵子を嫁にやることにきめた。

こうして、1936年(昭和11年)4月12日、勝と智恵子の結婚式は盛大に挙行された。 長女の結婚が滞りなくすんで、定五郎もハナもさすがに力が抜けたようであったが、それと同時に、親としての大きな役目を一つ果した満足感をしみじみ味わった。
定五郎は、農園の仕事をなお続けたいという勝の願いを入れてやり、自分は依然として共同貿易と東海商会の経営に専心し、業務は好調を続けていた。
星﨑一家に関する限りは幸福に満たされていたと言っても決して過言ではなかった。しかし、定五郎には大分前から心にかかることがあった。いや、それは定五郎一人だけでなく在留邦人全体の共通の悩みであったというべきであろう。
1932年(昭和7年)満州建国以来進出著しい日本に対するアメリカの感情は急速に悪化していた。東亜の空には暗雲が垂れこめ、遠くヨーロッパにおいてもドイツ、イタリアを中心に風雲ただならぬものがあった。
在留邦人は日に日に悪化する対日感情の中で、さらに何事か起ろうとする予感にとらわれ、世界情勢の推移を見守っていた。
ところが、1937年7月蘆溝橋に響いた一発の銃声は、ついに支那事変をひき起し、日本軍は支那全土に殺到した。一方、ヨーロッパでは1939年9月、ドイツがポーランドと戦端を開いたことによって、英、仏、両国は直に対独宣戦を布告して、第二次世界大戦の火蓋が切られたのであった。
在留邦人は大変なことが起ったと少なからず動揺したが、アメリカが中立宣言をしたことと、主要都市にはそれぞれ治安維持会が成立して、早晩日本に有利な解決が得られるだろうという希望的観測がなされることとで、一応平静に帰った。
明けて1940年、後に次女美枝子の夫となった石井忠が修学旅行の途中、北京に立ちよった時に北京飯店が売りに出されていることを耳にし、帰ってから父忠平にこの話をした。北京飯店は北京第一のホテルとして知られている。これが事実ならば大いに耳寄りな話なのである。忠平も、相談を受けた定五郎もひとしく触手を動かし、協議の結果、まず調査してみようということになり、忠平は直ちに北京へ向って出発した。

北京飯店
北京飯店が売りに出されているのは事実であった。経営者であるフランス人がヨーロッパに戦争が起ったため帰国することになり、急いで処分しようと奔走していることを忠平は確認した。そればかりでなく日本のホテル業者も北京飯店の入手に躍起となってせり合っているという情報もつかんだ。
この報が入ると、定五郎は川北弥三郎、倉田吉太郎等と相謀って、買収することに腹をきめると、直ちに北京へ出かけ、多くの競争者を蹴落して、その買収に成功した。そして、この買収に際し、弁護士、通訳として定五郎に協力し、また蔭の力として手腕を揮った者は、実に現運輸大臣楢橋渡氏(昭和34年当時)であったのである。
北京飯店は新旧二館に分れ、新館は間口75間(約136m)、石造7階建、旧館はそれよりやや小さい建物で、外観内容共に規模広大、まことに堂々たるもので、買収金額は20万ドルであった。
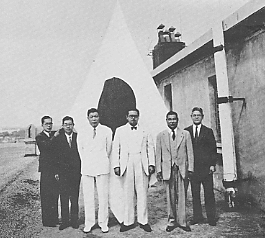
北京飯店の屋上にて(右から2人めが星崎氏)
定五郎は滞在3カ月の間に、みずから会長となり、社長には石井忠平をすえて、経営全般にわたる基礎を確立し、体制を整えた。
北京飯店は太平洋戦争末期まで、営業を続けたが、日本の敗色が濃くなるにつれて経営不能におちいり、さらに終戦後は中国に接収されたままで現在に及んでいるのである。
定五郎は故郷に立ち寄って久し振りに両親を見舞い、かねて東京の双葉高等女学校に遊学していた次女の美技子がちょうど卒業していたので、一緒に連れてアメリカへ帰った。
帰米すると、前々から考えていた通り、東海商会を智恵子夫婦に与えて、自分は共同貿易に専念することにした。
こうしているうちにも、日本とアメリカの関係は刻々に悪化しつつあった。1940年9月27日、日独伊三国同盟条約がベルリンにおいて調印されると、米国各紙の論調は真向から日本を非難した。10月には近衛首相の「最悪の場合対米衝突も已む無し」という談話が伝えられ、これに対しノックス海軍長官は「吾々は排斥された場合何時でもこれに応ずる用意がある」と述べるなどのことがあって、両国関係は緊迫のうちに年を越した。1941年、すなわち昭和16年は運命の年となった。
在留邦人はひとしく一触即発ともいうべき情勢の推移に心おののき、ひたすら円満な解決を願うのみであった。
しかし、その願いは容れられず、怖るべき日はついに来たのであった。
1941年12月8日(アメリカでは7日)の早晩、日本海軍が強行したハワイ真珠湾の大空襲によって太平洋戦争の幕は切って落とされた。
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:図書館 管理係
電話番号:0465-49-7800